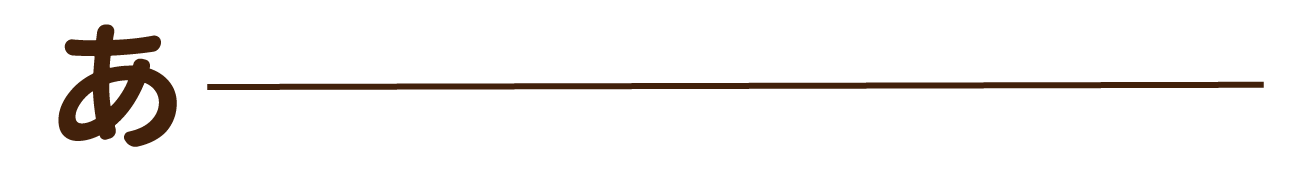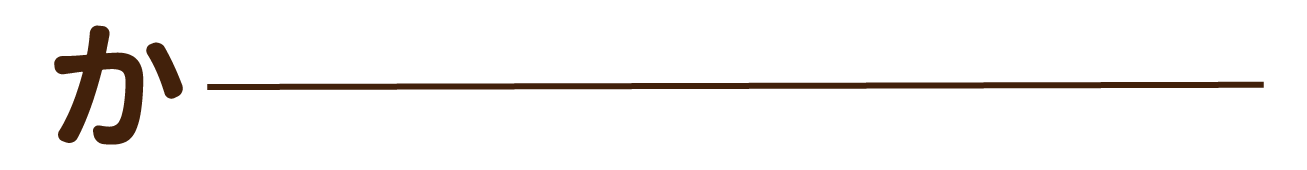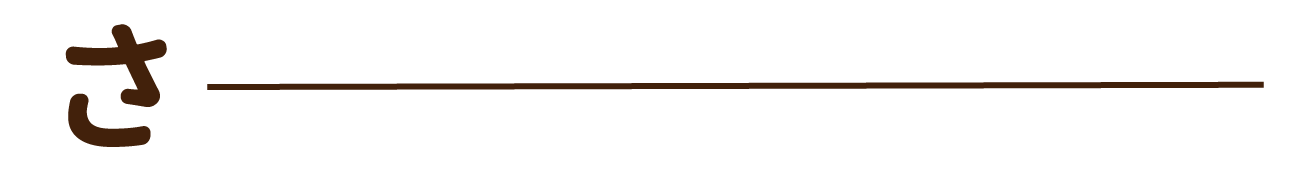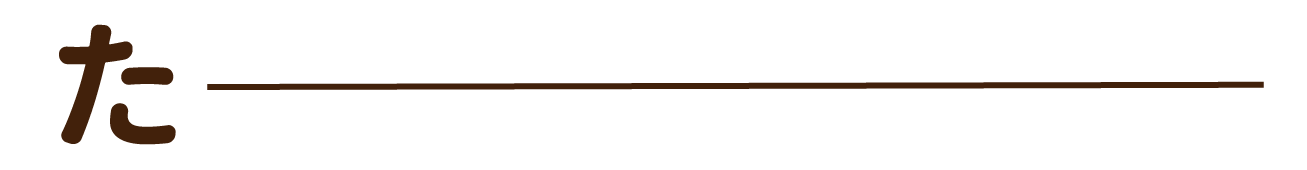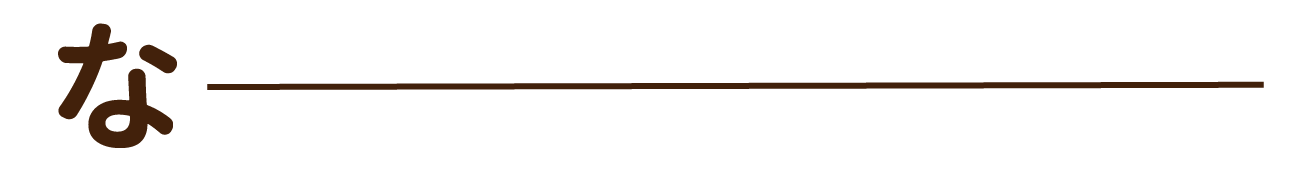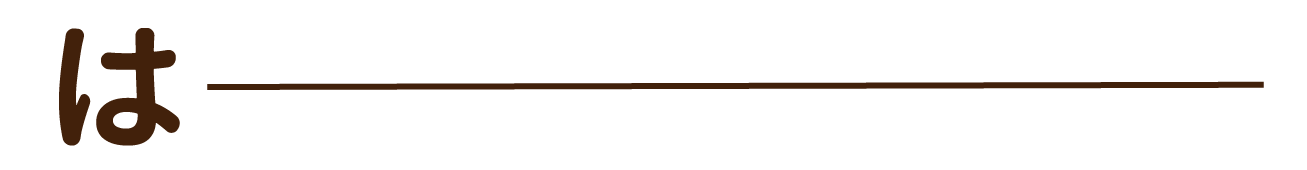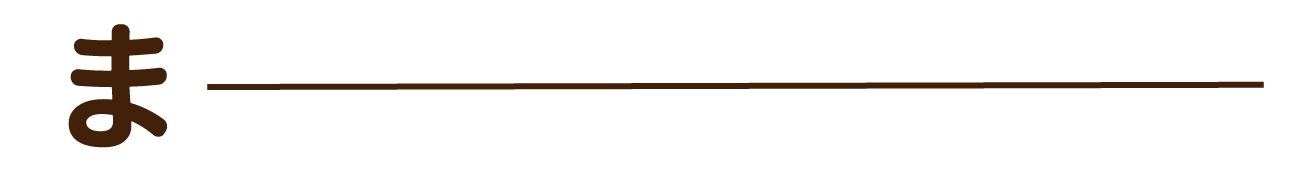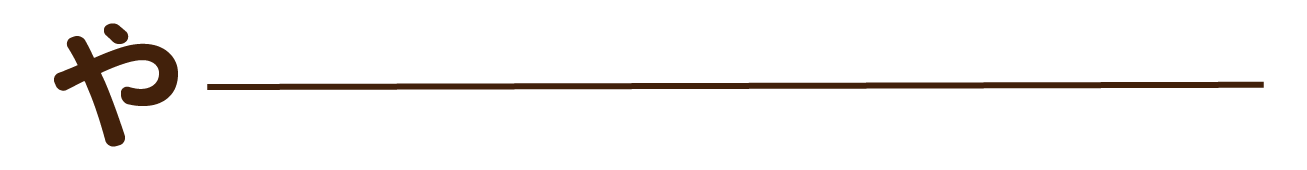- ホーム
- 症状別セルフケア

| い |
 |

|
胃炎
胃炎は、まずこの病気にかかった人はいないほど日常多いものです。「病気は気から」といいますが、心配事とか不安など精神的ストレスがあると、胃の粘膜は収縮したり、ただれたりします。これが続くと、胃炎や胃潰瘍になります。したがって、精神的な不安、緊張をとり除き、平穏な心をもつように修練しましょう。
また、お酒の飲みすぎとか暴飲暴食も胃炎の原因になります。昔の人は「腹八分目」といったように,胃腸に負担をかけないような食べ方、飲み方も胃炎防止に大切です。 しかし、痛みがひどいとき、熱があるときには医師にすぐ相談して、支持を受ける必要があります。早く手当てをしておけば、悪性化を防ぐことができます。
■ツボ治療法
6歳くらいまでの子どもの場合は、「手のひら療法」を行います。母親が自分の両手をよくもんで、手で熱を出し、子どもの背中と胃の上をなでます。
大人は灸。足の三里、梁丘、背中の肝兪、胆兪、脾兪、おなかの巨闕、不溶、天枢に灸をします。
■民間薬
①ハチミツ
3歳~6歳ぐらいまでの子どもは、ハチミツをスプーンに軽く一杯飲みます。
②ダイコン
ダイコンをおろして飲みます。
③ヒネショウガ
ヒネショウガをおろしたものをスプーン半分量、みそ汁か、おすましにまぜて飲みます。
④サイハイラン
ラン科の多年草サイハイランの根は沙列布と呼ばれ、薬用植物ですが、胃炎やその他の胃腸病に効果があります。1日量5~10ℊを煎じて飲みます。この植物の粘膜質が胃の粘膜を胃液などの刺激から保護してくれます。
⑤ゲンノショウコとセンブリ
煎じて、お茶がわりに飲みます。
⑥ハコベ
陰干しにしたものを煎じて飲みます。生のハコベをしぼって、汁を飲んでもよいです。
胃・十二指腸潰瘍
現代人5人に1人は必ずといってよいほど胃・十二指腸潰瘍で悩んでいるといってよいでしょう。その大部分の人は、精神的ストレスが原因だといわれています。
症例は個人によってまちまちですが、空腹時や食後2~3時間後などに腹部、とくにみぞおちのあたりが刺すように痛みます。
治療法は、精神の安定をはかること、十分な睡眠をとる、食事に気を付けること、日常生活を規則正しく送ることが大切です。潰瘍は、攻撃と防御の均衡が破れた時に形成されるといわれています。その攻撃の因子とは、胃液の中に含まれている酸度の高い塩酸やペプシンという、タンパク質を分解する酵素なのです。
胃液は亜鉛をも溶かすといわれているほど強カですので、胃液は食べた物を消化させるために、なくてはならないものです。また、胃の粘液に強い刺激を与えます。
結局は、胃・十二指腸潰瘍になる人の胃腸壁の粘膜は、 胃液に対して十分な防衛能力を持っていなかったからだということです。
それから、おなかの病気にかかりやすい人は、癇癪もちが多いです。心の修業をしましょう。 腹を立てるな、気を長く、心は丸く。
■ツボ治療法
マッサージ、指圧、鍼灸で、潰瘍を完全に治しましょう。背中の肝愈、胆兪、脾兪、胃兪、のど元の天突、気舎、おなかの巨闕、期門、中脘、足の三里、地機が主要なツボです。
■民間薬
①ジャガイモ
ジャガイモ1個をきれいに洗い、 発芽の部分を取り除き、皮のまますりおろし、1日1回、茶さじ1杯を飲みます。
②レンコン
レンコンのしぼり汁をつくり、さかずきに一杯ずつ飲みます。軽い出血ぐらいならこれで止まります。
③キャベツ
キャベツには潰瘍部を修復再生するカルシウムがいっぱい含まれています。キャベツの青汁をつくって飲むと効果的です。
 |

|
胃アトニー症・胃下垂症
胃アトニー症は胃液を作っている胃の筋力が弱って、消化不良がおこる症状で、神経質で無気力の人に多く、がっちりした体型のひとには少ないようです。原因は体質、暴飲、暴食、下剤などの濫用などですが、他の胃疾患から続発することもあるようです。
症状は、食後胃部の膨満感、重圧感があり、 暖気、悪心、便秘を伴うこともあります。
胃下垂は胃の位置異常で、胃の下が臍の高さよりも低くなることもあります。ときには骨盤まで達することもあります。
胃下垂は女性に多く、原因は体質、腹壁筋の弛緩、出産、開腹手術などによる腹腔圧の低下などです。
症状は胃アトニー症とほぼ同じです。
■ツボ治療法
へそ灸が有効です。へその上にガーゼを敷き、 すりおろしたショウガをその上にのばし、さらに日本紙をのせ、その上からビンポン玉より少し小さいくらいのもぐさをのせ、点火します。日本紙は4枚重ねにします。これを1日1回行います。ツボ治療は脾兪、肝兪、脾兪、胃兪、三焦兪、腹部は中脘、巨闕、足は足三里、陽陵泉、梁丘などを基本穴として使用します。
■民間薬
①ダイコン
おろし大根を毎日食べるようにします。ダイコンにはジアスターゼが含まれており、消化を助けます。
②トマト
ジュースにして飲むと、食欲不振、 胃のもたれに効きます。
③松葉
松葉を洗って、そのままかじってもよいのですが、ちょっと苦いので、低抗がある人は煎じてお茶がわりに飲みます。
④ゲンノショウコ
煎じてお茶がわりにして飲みます。
〈注意〉①便秘に気をつける。②よくかみ、談笑しながらゆっくり食べる。③食後は右下にして、30分は安静に。④睡眠を十分に。⑤腹式呼吸を毎日行う。⑥毎朝、食前に散歩、体操をする。 ⑦味つけは薄味にする。

| う |
 |

|
打ち身・ねんざ
打ち身(打撲症)は、ふつうは皮膚からの出血のないものをさし、皮下出血を伴います。したがって、患部が青くなり、はれてくると痛みます。
ねんざは、関節に外力が加わって、正常な運動範囲以上の無理な動きを強制されたもので、やはり痛みやはれを伴います。ねんざで多いのは足や膝、手の関節です。
打ち身でもねんざでも、軽いものから、まず冷湿布をして、熱やはれが引くのを待ちます。 冷やすことによって、出血や炎症が止まりますので、この時期の処置が悪いと、痛みが長引いたり、あとになって再び痛んだりします。ただあまり長く冷湿布を続けないこと。はれが引いたら、早く血液循環をよくすることが大切です。
■ツボ治療法
冷湿布などである程度症状がおさまってきたら、マッサージや鍼灸療法を行います。
手首では陽池、陽谷、大陵、足では血海、梁丘、膝では犢鼻、足首では太谿、照海、崑崙、解谿、申脈などから適切なツボを選んで治療します。
■民間薬
①シダレヤナギ
消炎、鎮痛効果があります。枝を折り、葉をいっしょにお湯が半量になるまで煎じます。この液で患部の温湿布にすると、とても効果があります。
②ニラ
軽いねんざには、ニラ30gをついて、その汁に、ショウガ汁を加えたもので湿布する と効きます。またついてドロドロになったものに、少量の塩を加えて湿布してもよいでしょう。
③ドジョウ
ドジョウを裂き、骨を抜いて皮のほうを患部に貼ります。はれて痛むものに消炎鎮痛として効果があります。
④アロエ湿布
生葉を皮ごとすりおろして、和紙か布に厚くのばします。これを患部に貼り、乾いたら新しいものととりかえます。
⑤キクの温電法
炎症がおさまったら、花を煎じた汁で患部を蒸します。

| お |
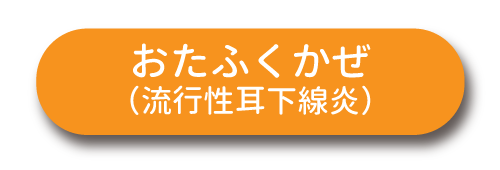 |

|
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
普通、耳下腺がはれ、顔がおたふくのようになるので、俗に「おたふくかぜ」と呼ばれています。幼児、学童がかかりやすく、冬から春によく流行する学校伝染病です。
ムンプウィルスというウィルスによる感染が原因で、耳下腺がはれてくるのですが、症状は軽いものから、重いときは発熱に伴って、頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐があって、患部は押すと痛みがあります。
おたふくかぜは、いちどかかると免疫になります。
耳下腺のはれがひどく、熱のある間は静かに寝かせることが大切です。はれた部分は冷やしてもよいのですが、温めたほうが気持ちのよいことが多いものです。
■ツボ治療法
伝染性の疾患ですから、医師のところで西洋医学的な処置をとるのが原則です。ツボ治療は、そのうえで対症療法として行います。
おたふくかぜの主な症状は発熱と耳下腺のはれですが、ツボ療法では解熱とはれによる頸部の痛みを抑えることに主眼をおきます。
解熱に対しては、38度以上の高熱の場合は、炎などの熱刺激を与えないことが原則です。それ以下の場合は、身柱、大杼、前腕部の尺沢といったツボに、棒灸かタバコ灸で熱刺激を与えます。
頸部の痛みをやわらげるには、手の小指の先に少沢というツボがありますから、ここに指ハリ、あるいはようじなどで刺激を与えてやります。
■民間薬
①ダイコンの冷湿布
大根おろしをたくさん作 って布に包み、痛むところを冷やします。耳の中がひどく痛む場合は、大根おろしをしぼった汁を2~3滴耳の中にたらし入れ、綿で栓をしておきます。また、ダイコンの葉を布袋にいっばい詰めた枕をさせます。熱が高いときに効果があります。
②アロエ
アロエをすりおろして患部につけますと、はれがひきます。
③ソバ粉
ソバ粉をぬるま湯でねり、これで患部を湿布します。
④スイセン
根をすりおろし、ガーゼに包んで、患部に貼ります。
⑤ユリ
ユリの根茎を乾燥させたもの40gほどを煎じて飲ませます。耳が痛むときに有効です。
⑥食塩水
ときどき、うがいをさせます。
| か |
 |

|
かぜ
かぜは上気道におこる急性のカタル性炎その他の疾患の総称です。
原因はウイルス感染ですが、誘因として寒さや、過労などもあげられます。
かぜは万病のもとです。こじらせると、思わぬ病気を併発しますから軽視できません。初期症状としては、鼻がかわく、クシャミ、ノドの痛みなどのほか、発熱することもあります。せきがでたり、関節痛、筋肉痛、全身倦怠のような全身症状をみることもあります。普通は1~2週間ぐらいで治ります。
とにかく、かぜをおこすウイルスの種類によって、症状や経過も様々です。
かぜをひいたら、安静、保護、栄養に気をつけるようにします。
■ツボ治療法
後ろ首の風府、風池、背中の大椎、大杼、風門、肺兪、のど元の天突、鎖骨下の中府、手の孔最、合谷などの諸穴に鍼や灸、あるいは指圧・マッサージを行います。東洋医学では、風の邪気は最初に背中の風門から入り、それが後頭部の風池にたまり、さらにその上の風府に集まるといわれています。したがって、この3つのツボは重要です。
■民間薬
①タマゴ
日本酒50gに卵2個を入れ、砂糖を加えてよくかきまぜて飲みます。
②梅
かぜのひき始めで熱の高い時には梅干し1~2個を黒焼きにし、これを茶碗に入れ熱湯 を注ぎ、飲みます。
③ショウガ
ショウガ6gをすりおろして熱湯を加え、蜂蜜を入れて飲みます。
④クマ笹
エキスを適量に薄めて、うがいをしながら飲みます。
⑤ネギとみそ
ネギを細かくきざみ、大さじ山盛り1杯をごはん茶わんに入れます。それと適量のみそとカツオ節を加え、熱湯をいっぱい注いで飲みます。そして夜具を厚く重ねて寝ると、発汁を催して力が抜け去ります。
⑥ニンニク
5~6片焼いて食べますと、卓効があります。
肩こり
長時間同じ姿勢で仕事をしたり、根をつめて文字を書いたり、編物をしたりすると、首の後ろから背中にかけて、筋肉がこわばり、痛くなることがあります。
これらは、不自然な長時間の姿勢、あるいは目の使いすぎ、精神的ストレスなどによって、首や肩、背中の筋肉の血のめぐりが悪くなり、こり症状を起こしたもので、一種の筋肉痛です。
肩こりは健康な人でもなりますが、胃腸の調子が悪い人や、太りぎみで血圧の高い人が起こりやすいものです。
いずれにしても、人間の肩や首、背中の筋肉は常に無理がかかっていて、疲労しやすい状態におかれています。こり、痛みを感じる場所を確認して、ツボ治療法を行えば効果があります。
■ツボ治療法
後ろ頭の天柱、風池、肩の肩井、背中の曲垣、膈兪、肝兪、腰の大腸兪がポイントになるツボです。胃腸の弱い人で、肩のこりやすい人はおなかの中脘、天枢、大巨にも治療をします。
軽い肩こりなら、肩関節の体操、胸反らし、前かがみ運動で取れます。両手でほうきの柄や棒など持って腕の上げ下げ運動をすれば、肩こりのよい治療になります。ぬるめの湯にゆっくり入り、肩のマッサージをするのもよい でしょう。
■民間薬
①キハダ
黄柏末を漢方薬局・薬店で求めて、このキハダに酢を加え、ドロドロになるくらいに練り、これにヒネショウガのおろし汁と卵白を加えてまぜ合わせ、それを布などにのばして、患部に貼ります。
②ヘチマ
果実を日干しにし、切って粉末にしたものを、約10g飲むのも効果があります。
③テンナンショウ
粉末にして小麦を少量まぜ、それに酢を加えて、よく練ります。これを布などにのばして、痛むところに貼ります。
④トウガラシ
粉末にし、ごはんつぶを加えてよく練ります。これを布や和紙の上にのばして、患部に貼ると効きめがあります。
⑤マタタビ
茎約15gを水540mlで煮つめ、半量ほどにします。これを1日分とし、3回に分けて、毎食前に飲みます。
 |

|
肝硬変
急性肝炎にかかった人で、そのまま完治せず 慢性肝炎に移行する人がかなりいます。はじめは自覚症状がありませんが、病気がすすむと肝臓が硬くなり、腹に水がたまり、脾臓や陰のうがはれ、食欲不振になり、便秘したり下痢したりします。予防のためには定期的な検査が大切です。また過労とならぬように注意し、規則正しい生活を営んでください。
肝硬変の主要な原因としては、ウイルスとアルコールがあげられますが、日本では大部分がウイルスによるもといわれています。
食事療法としては、肝細胞の再生、修復のためにも、十分にとらなければなりません。バランスのよい栄養を、過不足なくとるように心掛けることが大切です。アルコールは厳禁です。
■ツボ治療法
背中の肝兪、胆兪、胃兪、のど元の天突、気舎、腹部では期門、中脘、足の三里、地機が主要穴です。
また手の平療法も有効です。両手をよくもみ、こすって、熱を出し、その手を疾思部にあてて、よくさすってください。「病に負けてなるものか」という気力も大切です。
■民間薬
①ショウガ湯の温湿布
ひねショウガ50gを皮のまますりおろし、水綿袋に入れて、これを1 ℓの水に入れて煮立てて、熱いショウガ湯を作り、タオルをひたして右肋骨下部を温めます。冷えたら取りかえ、30分くらい繰り返し、1日 2~3回くりかえし、温湿布するとよいです。
②クマ笹
エキスが市販されていますが、よく効く薬です。
③コンフリー
粉末(市販) を求めて飲むか、自分で裁培するとよいでしょう。生のままで食べてもよいし、お茶がわりに飲んでもよいです。
④カンゾウ
主成分のグリチルリチンが肝臓に対して優れた作用を及ぼします。濃いめに煎じて、お茶がわりに飲むと効果があります。
⑤カワラヨモギ
葉茎の煎じたものをお茶がわりに飲みます。
肝臓病
全身がだるい、疲れやすい、食欲がない、吐き気がする、おなかがはるといった自覚症状のあるときは、肝臓病を疑って見るべきだと思います。特に強調したいのは、肝臓病は慢性になりやすいということです。そして「沈黙の臓器」という異名のあるように、鈍感で症状の出たときは、ある程度進行しているという危険がある臓器なのです。
肝炎は肝臓の細胞が炎症を起こし、肝臓全体がおかされてしまう病気です。肝臓病の中で一番多いのが肝炎で、その原因によって、A型肝災、B型肝炎、非A非B型肝炎、アルコール性肝炎などといういろいろな型に分類されます。食欲不振、吸吐、高熱、微熱、頭痛、黄疸、倦 怠感などがあります。
■ツボ治療法
一度肝臓病にかかると、完全に平癒しているかわからないのです。肝臓は鈍感な臓器なので、病気を治すつもりで飲む薬も、元をただせば化学物質なのですから、完全に平癒させるのには漢方療法です。按摩、指圧、鍼灸などでツボ治療をします。背中の肝兪、胆兪、脾兪、胃兪、おなかの中脘、大巨で腸の調子を整えます。足の三里、地機にも施術すること。
■民間葉
①シジミ
シジミに水同量を1時間ほど煮出し、シジミを取り出します。残った汁は、さらに2.5mlに煮つめて煎薬として一日3回に分けて飲みます。
②ニンジン
急性肝炎で黄疸の強い人に効果的 です。乾燥させたニンジン12gを煎じて、1日 2回飲みます。
③シイタケ
A型肝炎には新鮮なシイタケが用 いられています。
④キャベツ
肝臓の機能を強化するのがビタミンKです。キャベツなどビタミンKを豊富に含んだ食物を多くとることが大切です。
⑤リンゴ
黄疸が出たら、リンゴとハチミツが 有効です。リンゴ1個をすりおろして、ハチミツ大さじ1杯を加えて食べ、あとは何も口にしません。1日5回ほど食べます。

| き |
 |

|
気管支ぜんそく
気管支ぜんそくは、気管支が狭窄をおこすことによる、喘鳴を伴なった発作性の呼吸困難を示す病気です。はじめは空セキで、はげしくなると、のどがむずがゆく痛みを感じ、とくに吐く息が苦しくなります。
気管支ぜんそくの発病は、アレルギーと気道の過敏性によるものです。ぜんそくをおこすアレルゲンにはいろいろありますが、室内塵が重要です。家ダニ、カビ類、花粉などがその主なものです。その他、寒さ、過労、喫煙、酒の飲み過ぎなどもその誘因となります。
気管支ぜんそくは治りにくい病気で、根治することはなかなか困難ですから、早期治療が大切です。
■ツボ治療法
背中の大椎、治喘、肺兪、心兪、のど元の天突、胸の中府、膻中、腹部の中脘、天枢、腕の孔最、俠白などが重要なツボです。指圧、マッサージを併用することもよいでしょう。
発作がおこったときは、後ろ首の天柱から背骨の両側を腰部に向けてマッサージします。
また、朝晩5分ずつ、のど、胸、肩の甲、背中を乾布マッサージすると、気管支ぜんそくの予防になります。
■民間薬
①オオバコ
オオバコ15gを水600mlで半量までに煎じ、1日3回に分けて飲みます。
②フキ
茎を3cmくらいに切って、薄味のしょうゆで煮て食べたり、また葉を細かくきざみ、しょうゆをつけて食べます。
③ニンニク
ニンニク1個を蒸し焼きにして、毎日食べます。セキのひどいときは、ニンニクの葉または根のしぼり汁を20滴ほど飲めばせきもとまります。
④ハチミツ
湯飲みに熱湯を注ぎ、その中にハチミツを入れてよくかきまぜて、毎晩就寝時に飲みます。
⑤レンコン
節をおろしたものさかずき1杯にひねショウガのおろし汁スプーン1杯、さらにレンコン実ごとおろしたものと砂糖を少々加え、熱湯を注ぎ、かきまぜたものを飲み干します。
狭心症
心臓に血液を送っているのが冠状動脈ですが、この冠状動脈が硬化して心臓に十分に血液にゆきわたらなくなったときに起こる障害が狭心症です。
冠状動脈硬化症の起因は、有力な説として、老化現象、高血圧およびコレステロールの蓄積の3つが合併している場合が多いとされています。
狭心症の発作の症状は、一般には胸骨の裏側に痛みが現われ、それが左肩から左腕に広がると、前胸部がぐっと締めつけられるような、重いようななんともいえない不快感に襲われます。発作は数分から数十分続くことがありますが、肋膜炎とまちがえられることもありますので、注意をしましょう。
■ツボ治療法
まず、絶対に安静を保つようにしましよう。ツボ治療法は、背中では心兪、胸は膻中、腹部で巨闕、手では郄門、神門などがポイントになります。とくに郄門は動悸や息切れ、胸苦しい、胸痛がするといったときの特効穴です。
また、手の左の小指の爪のもとに少衝というツボがありますが、緊急なときは、ここをかむ と発作がやわらぎます。
■民間薬
①クマ笹
エキスは新陳代謝、血液循環をよくしてくれます。
②ドクダミ
乾燥させたドクダミを1日量で120g煎じて、お茶がわりに飲みます。高血圧症、動脈硬化、脳出血の予防になります。
③シイタケ
血液中のコレステロールを減らし、コレステロールの吸収を妨げる働きがあるため、高血圧や動脈硬化症の予防となります。生シイタケや干シイタケを常食し、その煎じ汁を飲みましょう。
④ラッキョウ
ラッキョウを毎食3粒ずつくらい食べましょう。漢方では蓮白といって、干したラッキョウを狭心症の薬として使用します。
⑤トマト
トマトは悪玉コレステロールの吸収を防ぎ、また体外への排出を促進するといわれています。

| け |
 |

|
下痢
水分の多い便を下痢便といいます。身体に悪いものを食べたり、細菌が体内に侵入した時に起こす下痢は一種の生体防御反応です。この場合は、単に下痢止めを飲むだけでは解決しません。同時に原因疾患の治療を行わなければなりません。下痢の時は、とくに水分を十分にとり、脱水を防ぐことが大切です。
ツボ治療の対象になるのは、とくにはっきりした原因がなく、消化器系の検査などでも異常がないのに、どうも下痢をしやすくて困るという場合です。あるいは、ふだんは便秘がちなのに、精神的な緊張があった場合に下痢をするというものです。
ただし、慢性化したら、専門医にみてもらいましょう。
■ツボ治療法
腰の大腸兪、小腸兪、おなかの肓兪、大巨、足の三里、腕の手甲の温溜などのツボに、3~5壮の灸を毎日行うとよいです。
■民間薬
アカシアの葉と枝をまぜて、一つかみを500mlの水で3分の1まで煎じて飲みます。
②ニンニク
かぜなどによる細菌性の下痢には、 5~10%のニンニクのしぼり汁で浣腸します。 同時にニンニク5個、ダイコン60gを煮て食べます。
③ニラ
腸炎による下痢には、ニラのおかゆを食べましょう。
④リンゴおろし
ひどい下痢には、リンゴをおろして食事がわりに食べると、とても楽になります。
⑤シソの葉
慢性の下痢に効きます。シソの葉 をつとめて食べるとよいでしょう。
⑥インゲンマメ
葉をつんで煎じるだけで胃を整え、下痢を治す薬になります。コップ半合ほど飲みます。

| こ |
 |

|
口内炎
口内炎はいろいろな疾患に併発して、口の中の粘膜が荒れて痛む病気です。単純なものは、熱いものを飲んだり、歯で唇や舌を噛んでも起こすことがありますが、風邪や胃腸障害でも起こり、重症なものでは潰場をみることもあります。その場合はかなりの苦痛です。
症状の程度により、いくつかに分類されておりますが、最も多いのはアフタ性口内炎です。これは再発性のもので、いちど治っても体の調子によって何度でも再発しやすくなります。これにかかるのは女性に多く、最初にかかるのは 20歳前後です。
これを治すには、何よりも原因をはっきりさせることですが、口内炎の多くは原因がはっきりしないというのが実態のようです。
■ツボ治療法
顔面では地倉、背中では大椎、治喘、膈兪、肝兪、脾兪、おなかでは中院、天枢、手で合谷、足で足三里などが治療穴です。これらのツボには、指圧でもよいですし、お灸、鍼をするのも 効果的です。
■民間薬
①ナシ
ホットジュースにして飲みますと、口内が乾燥する口内炎に効果があるといわれております。
②おろしダイコン
口の中に苦みを感じたりしたり、食欲もあまりないような口内炎のときは、おろしダイコンを、毎食事時に茶碗に三分の一ほど食べたり、おろし汁で口をすすぐと効果があります。
③トマトジュース
口の中に腫脹や潰瘍のみられるときに、トマトジュースを口の中に数分間含み、そのあと飲みます。これを一度に2~3回繰り返しますと、効果があるようです。
④ハチミツ
ハチミツを8倍の水でうすめ、これで1日に何度もうがいします。
⑤アロエ
すりつぶして、その汁でうがいをします。
高血圧症
高血圧症の85~95%は、遺伝的な因子以外に 原因が明らかでない本態性高血圧症です。その他は症候性高血圧症といい、腎臓の昇圧因子が関係するもの、内分泌機能の変化によるもの、神経が関与するもの、心臓の送血量が増加するものなどの症候として起こるものです。
高血圧症は動脈硬化、脳卒中、狭心症、心筋梗塞、尿毒症などの生命の危険を伴う成人病を誘発するものとして、現在最も警戒されているものの一つです。とくに動脈硬化の進展が早い点が目立ちます。
高血圧が長くつづくと脳・心臓・腎臓などに 病変が起きて、生命をうばいかねなくなりますから、根気よくコントロールすることが必要です。
■ツボ治療法
食塩の摂取を控えめにし、食べすぎ、過労、ストレスなどにも気をつけましょう。頭の百会、 後ろ首の天柱、背中の肩井、膈兪、心兪、腰の腎兪、のどの人迎、腹部の中脘、大巨、手の合谷、足の三里、三陰交、湧泉などが主要なツボです。
■民間薬
①クコの葉
クコの葉を生で食べてもよいのですが、普通は乾燥した葉をクコ茶として毎日飲み続けます。クコ茶は濃いめにします。
②ニンジン
1回に100gをしぼり、そのジュー スを1日2~3回に分けて飲みます。
③クマ笹
クマ笹エキスはコレステロールの除去、血液粘稠度の調節、肝臓の解毒や腎臓の利尿作用などの促進などの諸作用があるといわれており、腎性高血圧症などにはよいと思われます。1日3回続けて飲みます。
④コンフリー
青汁を毎日、食前1時間~30分前に100mlくらい飲みます。
⑤エンドウ
しぼり汁を1回に茶碗半分ぐらいの量を温めて飲みます。
⑥ドクダミ
1日量15gを煎じ、お茶がわりに飲みます。
<注意>血圧が上がる時。イライラ、発熱、走っている時、冷たいものを飲む、冷たい空気にさらされる、水中に飛びこむなどは、緊張と同様に血圧を高くします。
反対に温かいものを飲むとか、入浴などは、リラックスするのと同様、血圧を下げます。
ただし熱い浴槽中にあまり長くはいっていると、いったん下がった血圧が上ってきます。高血圧症の人は、熱い長湯はよくありません。ぬるめのお湯にゆっくりと入るのがよいのです。
コーヒーを1日なん杯も飲む人がいますが、コーヒーは血圧上昇剤です。ワサビ、トウガラシ、カラシ、朝鮮ニンジンも上昇剤です。
反対に海藻類にはごく少量のヨードやアミノ 酸を含んでいるものもあって、動脈硬化の予防に役だつといわれています。塩のとりすぎも動脈硬化を促がし、血圧を上げます。野菜、くだもの、酢の物は動脈硬化予防にプラスです。ごまあえ、納豆もプラスです。ただし、めまい、手足のしびれ、はげしい頭痛、吐きけ、胸の痛み、眼底出血などの症状が あらわれている場合は、必ずお医者様にみてもらいましょう。
足の裏を叩くだけで血圧が下がる
血圧が高い人は、うつ伏せに寝て、足の裏を家族の誰かにトントンと左右100回くらい叩かせると、血圧が下がると、芹澤勝助先生はおっしゃっています。 自分で叩く場合はリラックスして座り、足首を持って叩きましょう。
 |

|
更年期障害
閉経期を更年期といいますが、この時期にみられるホルモンのバランスの変調による自律神経機能の不安定な状態が更年期障害です。
更年期障害は閉経の3~4年前から始まり、症状として、頭痛、めまい、耳鳴り、動悸、息切れ、肩こり、腰痛、胃腸障害などがあり、心身症になることもあります。
更年期障害は加齢による生理的変調ですから、不安感を克服して、この時期を乗りこえましょう。
東洋医学ではこのように女性の自律神経失調症に似た状態で月経やホルモンの異常に関連して起こる諸症状を「血の道症」といっています。 体内の気と血の流れが悪くなって滞るために起こる症状だと考えているのです。
■ツボ治療法
頭の百会、後ろ首の天柱、肩の肩井、背中の厥陰兪、臀部の上髎、胞肓、腹部の肓兪、大巨、 関元、足の三陰交、太谿、血海などが中心となるツボです。症状に合わせてツボを選び、気長に鍼灸治療をすると非常に効果があります。
■民間薬
①ネギ・シソ
イライラする人は、シソの葉とネギのスープを飲むと気持ちが落ちつきます。
②ハーブ茶・ゲンノショウコ・皮つきのクワの根
乾燥品でそれぞれ3gを700mlの水で、半分になるまで煎じた汁を飲みます。
③コウホネ
スイレン科の多年草です。このコウホネには、婦人病、更年期障害など女性特有の諸症状に効果があるといわれます。乾燥した根茎5~10gを1日量として煎じて、1日3回飲みます。
④サフラン
メシベ10本を熱湯に加え茶わんに入れ、淡紅色になるまでおきます。その上ずみをさめたら飲みます。色の出るあいだは何回でも使います。
⑤クズ
頭痛や肩こりのひどい人は1日20gを煎じて飲むと、よく効きます。
五十肩
五十肩と呼ばれる症状は、肩関節のまわりにある筋肉や腱の老化、変性によって起こります。五十肩は無理に動かすと痛むのですが、とくに後頭部に手をやるとひどく痛いので、髪を結ったり、帯を締めることができなくなります。五十肩は誰でも多少はかかる症状ですが、近年は寿命が延びたため、60歳代の五十肩もまれではなくなりました。
五十肩は痛むからといって動かさないと、なかなか治りません。お風呂上りに首、腕の関節、腰の運動を、むりのないようにすると、早く正常の体にもどります。たとえば、痛くないほうの手で体を支えて、思い切り痛むほうの手を前後に振ったり、ひじをまっすぐに伸ばし、頭の上に左右に振るといった情の体操は、痛みをやわらげますし、五十肩の予防にもなります。
■ツボ治療法
肩先の肩髃、肩甲骨の天宗、肩から少し下がったところにある臂臑、鎖骨の下の中府、腰の腎兪の5つが五十肩の特効ツボです。
治療のコツは、まず肩を温湿布で温め、さらにツボをマッサージ、指圧します。痛みには炎治療がよく効きます。とくに手が後ろに回らないときは、腎兪、天宗、肩髃、手が横や前に上がらないときは肩髃、腎臑、反対側の肩のほうへ上がらないときは中府を中心に治療します。
■民間薬
①梅干し
毎日2個ずつ食べます。梅に含まれるクエン酸は有害な老廃物を体外に排出する作用があるので、体の中から治していきます。
②レモン
しぼり汁を茶さじ1~2杯ずつ、1日3回飲みます。水や湯で薄めて飲んでもよいでしょう。梅干しと同様の効果が得られます。
③ヘチマ
実を切って乾燥させて粉末にします。これを1日に10gほど飲みます。
④ショウガ
すりおろしてしぼった汁を、痛む肩や腕にすり込みます。発汗作用と同時に血行がよくなります。また、ヒネショウガをすりおろし、木綿袋に入れて湯の中で煮立て、その湯液にタオルを浸してしぼり、温湿布をしても有効です。冷えたらとりかえて、2~3分間蒸しつづけます。1日2~3回行うとよいでしょう。
| さ |
 |

|
産前・産後の異常
お産の前後には、さまざまな症状が現われます。お産前半期では流産、子宮外妊娠も重大な異常です。妊娠後半期にはしびれ、むくみ、血圧上昇、たんぱく尿、めまい、おりもの、などいろいろな症状が出ます。出産後は、神経疲れ、性器からの細菌感染などが起こりやすく、注意が必要です。
流産しやすい人は、いちばん悪いのは夜のおつとめです。昔は初産のときは、実家に帰って子供を産み、日数がたって完全に子宮が収縮する頃を見はからって、婚家へ帰ったものです。すなわち、28日から1ヵ月ぐらいで妻の役目ができるようになってから、実家の親は娘を婚家に帰したのです。 産後は2週間目から朝晩ふとんの中で10分くらい運動をすること。また日光浴をしましょう。便秘にも気をつけてください。良質のタンパク質、季節の野菜、新鮮な果物の摂取を心がけましょう。
■ツボ治療法
症状に応じたツボ治療を行いますが、一般的には、腰の腎兪、臀部の次髎、胞肓、おなかの期門、肓兪、関元、足の三里、血海、陰陵泉、三陰交、太衝などが中心となりましょう。
■民間薬
①ハスの実
早産、流産予防に、ハスの実の芯を抜いたものをおかゆにまぜて食べます。
②ハコベ
産後の肥立ちにハコベを用います。乾燥させたハコベ全草20gを1日量として、煎じて飲みます。
③イタドリ
出産後の新陳代謝がうまくいかないために起こるむくみに、イタドリの根20gを1日量として、煎じて飲みます。利尿効果で、むくみがとれます。
④黒マメ
妊娠中、胎動腹痛がある時には、黒豆90gに清酒60mlを加え、とろ火で煮込み、爛熟させたものを食べると効きます。
⑤ホオズキ
産後の子宮出血に用います。子宮を収縮させる作用があり、止血に役立ちます。また産後の乳汁不足にも有効です。乾燥したホオズキの根を煎じて飲みます。

| し |
 |

|
子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮の筋層中にコブの芽(核) ができて、次第に大きくなる良性の腫瘍です。 大きさは、肉眼でやっと認められるぐらいのものから、子供の頭大のものまで様々です。
主な症状は、月経期間が長びき、月経血量が増加し、月経周期が短くなり、月経痛、月経異常、子宮出血、疼痛、隣接臓器の圧迫などですが、自覚症状がまったくない場合もあります。生理の前後に軽い腰痛があったり、肩こり、頭痛、手足が冷えたり、胃痛などが起こることもあります。
このように、子宮筋腫は無症状で治療の必要のないものや、症状があって薬で軽くできるものもあります。しかし素人判断は危険で、医師の指導で対策をたててください。
■ツボ治療法
頸部から肩背部をホットパックで温めたあと、後ろ首の天柱、肩部では肩井、曲垣、背中では肺兪、心兪、隔兪、腰部では腎兪、大腸兪、膀胱兪、次髎、志室、胞肓、腹部では中極、大赫、 中脘、天枢、大巨、足では三陰交、陰陵泉などの諸穴を使用します。
■民間薬
①コンニャク
コンニャクを2~3分ゆでて、熱くしたものを布に包んで、片方の足首から鼠蹊部にかけて、冷えている部分、こりのある部分にパックします。
②オオバコ
葉または実を煎じて飲みます。また、1日数回の塩湯を腰湯として併用すると、さらに効果が上がります。
③タンポポ
根や若葉、花などを乾燥保存させ、これを1回に根なら4~8g、葉花なら8~9gを煎じて、食前30分に飲むとよいでしょう。
④キカラスウリ
根を乾燥したものを1日5~15g煎じて飲みます。
⑤ヘチマ
種子10gを煎じて飲みます。また、実を黒焼きにして飲んでも効きます。
⑥トクサ
茎3~5gを煎じ、1日2~3回に分けて飲みます。
湿疹
湿疹は俗に「くさ」とも呼ばれ、皮膚病の中で最も多いものです。広い意味では、湿疹というと接触性皮膚炎やアトピー性皮膚炎も含まれますが、普通はこういう特殊な湿疹以外のものをいいます。
その原因ははっきりしていないことが多く、 体のいろいろな状態が関連しているようです。特徴は、かゆみがあること、および小さい点状の発疹が固まってできることです。
湿疹は体質が深くかかわっていると考えられますので、塗り薬だけで根治するのは困難です。これを治療するには、単に皮膚だけでなく、全身病としてとらえ、体の内部から治して、体調をととのえ、体質の転調をはかることに重点を 置くのがよいでしょう。
■ツボ治療法
背中の肺兪、肝兪、胃兪、腰の三焦兪、腎兪、大腸兪、腹部の中脘、巨闕、天枢、手の曲池、手三里、合谷、足の足三里、三陰交などがよく使われます。
■民間薬
①クサノオウ
湿疹(クサ)の王といわれ、皮膚病によく効きます。生葉の黄色の汁をつけます。
②クマ笹
エキスをうすめて患部につけると、かゆみや痛みがとれて、皮膚がツルツルしてきます。
③キク
キクの葉をガーゼで包み、よくもんで、汁をしぼります。これに酢を少々たらして、患部に塗りつけます。俗に胆毒と呼ばれる乳幼児の頭部の湿疹によく効くといわれています。
④アロエ
アロエの葉をはいで、ぬるぬるの面を皮膚に当てること。化粧水をつけるように。
⑤ドクダミ風呂
干した葉を布袋に入れて、ドクダミ風呂にすると効果があります。
(注) チョコレート、ココア、エビ、カニ、イカ、魚、卵、タケノコ、モチなどの過食をさけることが大切。これらが刺激になるからです。
 |
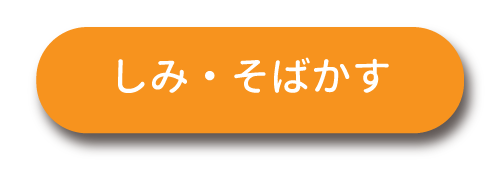
|
歯槽膿漏
歯槽膿漏は虫歯のように歯そのものの病気ではなく、歯をささえている歯周組織の慢性進行性の病気で、歯がぐらついてくるものです。
すなわち、歯ぐきの中の歯槽骨という部分がこわされ、いったんこわされると、元通りにするのが難しいのです。
口臭、口中の粘つきが気になるようになりましたら、歯槽膿漏の初期症状であることが多く、歯ぐきが赤みを帯びてブヨブヨしてきたら、まず歯槽膿漏と考えてよいでしょう。放っておきますと、歯のつけ根があらわれてきて、ついには歯が抜け落ちてきますので、ひどくならないうちに治しましょう。
ツボ治療法は、歯槽膿漏が初期の段階ですと、根気よく治療すれば効果が出てまいります。
■ツボ治療法
口や歯の周囲の大迎、巨髎、四白、下肉、頬車などを中心として、後ろ首の天柱、腰背部の肝兪、腎兪、腹部の中脘、肓兪、天枢、手の三里、曲池、合谷などの諸穴が対象になります。 歯の痛みを伴うときは、合谷を処置すると効果があります。
■民間薬
①ハコベ
葉をフライパンで炒り、これをすり鉢ですって粉末にし、塩とまぜて歯ブラシにつけ、歯をみがきます。塩は殺菌作用と歯ぐきを引き締める働きがあります。
②サンショウ
果皮を酢で煎じ、歯ぐきにつけます。口に含んで少しずつ飲んでもよいでしょう。
③ダイコンおろし
ダイコンおろしを軽くしぼって塩をまぜ、歯と頬との間に入れておきます。ダイコンのビタミンCと消化酵素の働きで、歯ぐきのはれがひきます。
④ユキノシタ
葉(裏が淡緑色のもの)1枚をよく洗い、塩もみしたのをまるめて、歯ぐきをよくマッサージします。
⑤キュウリ
血液を浄化する作用がありますので、生食すると有効です。
しみ、そばかす
しみは肝斑といって、顔面とくに眼のまわりに対側性に発生することが多く、境界もはっきりしています。女性に多く、季節的には夏期にできやすくなります。また、妊娠や婦人科疾患に伴って発生することも多く、原因はよくわかっていません。
そばかすは雀斑といって、顔面や手背などに多くみられ、夏期に濃くなります。5~6歳頃より発生し、思春期に増強します。遺伝性が強く、優性遺伝をします。
しみやそばかすには、強い日光光線が最もよくありません。また過労、睡眠不足、精神的ストレスに注意をし、皮膚に刺激となる化粧品にも気を遣って、予防に心がけるようにしましょう。
■ツボ治療法
背中の肺兪、腰の三焦兪、胃兪、命門、胸の膻中、腹部の中脘、陰交、手の陽池、合谷、内関、太渕、足の太谿などがポイントになります。
しみ、そばかすは短時日の間に治すことは難しいですが、ツボを使った治療によって、体質、体調をととのえていけば、自然治癒することは十分考えられます。
■民間薬
①アズキ
そばかすに用います。アズキを炒ってから粉末にし、その3分の1の量の米ぬかをまぜ、それをガーゼに包み、これを熱湯につけます。これで1日2~3回、5分間ほど患部をまさつします。
②酢卵
卵を200mlの米酢の中に入れ、2昼夜ぐらいそのままにしておきます。そのあと皮だけ取り出し、残った卵白、卵黄と米酢をよくかきまぜ、これを飲みます。
③アマドコロ
葉と茎をすりつぶし、その汁を患部に塗ります。
④アロエ
アロエの芯のゼリー状のところを、直接皮膚にすりこむようにします。風呂上がりなどに、ゆっくりすりこみます。
⑤黒砂糖
水でどろ状にとき、湯上がりに約30分、マッサージしながらすりこみます。
 |

|
しもやけ
しもやけは、寒さや冷えのために体の末梢の毛細血管の機能が鈍り、手足に貧血やウッ血が生じるために起こる病気です。そのために皮膚が赤黒く変化し、腫れ上がってきます。
手や足の先は、正常な人なら30~34度くらいあるものですが、人によっては氷のように冷たくなっています。しもやけは、このような状態になっている人に起こりやすいものです。とくに貧血性の人、子どもに多くみられます。
ひび、あかぎれなども皮膚から分泌される皮脂と、汗の量が適度に保たれていない場合、内臓のぐあいが悪い場合、あるいは血液の循環が悪く、栄養が皮膚に行き渡らない場合に起こりやすいものです。このような状態は、寒さや冷えが引きがねになって起こりやすくなります。
■ツボ治療法
背中の大椎、肺兪、肝兪、腰の腎兪、大腸兪、腹部の巨關、中脘、天枢、手の陽池、合谷、足の三陰交などがポイントになります。
こうしたツボ刺激は、寒さに向かう晩秋あたりから行っていくと、しもやけの予防となります。しもやけにならなくなると、目に見えて体も丈夫になってきます。
■民間薬
①ニンジン
すりおろした汁を患部にすりこみ、よくマッサージをします。数日間続けると、次第に効果があらわれます。
②ミカン
5個分の皮を内側の白いところを削ぎ落として、カラカラになるまで乾燥させます。これを炒り、そのあとすって粉末にします。これに根ショウガ少々と水を加えて、煎じます。 さめてから、患部に塗布して用います。
③赤トウガラシ
赤トウガラシは、しもやけの予防に適しております。用法は赤トウガラシを3~4本ちぎって紙に包み、靴やスリッパの爪先に詰めて用います。皮膚を刺激して血行をよくします。
④ネギ
白い部分を水でやわらかくなるまで煮た汁を、就寝前に患部に塗り、15分くらいたってから湯で洗い落とします。
じんましん
じんましんは、突然かゆみを感じて発疹がで き、これが数分~数時間で痕跡を残さないで消えてしまう病気です。
一般的には、抗原抗体反応としてアレルギー性に起こりますが、そのほか、温度の変化や日光などによるものや、けがや手術などの際の反射性に起こるもの、精神性に起こるものなどがあります。全身のどこの皮膚にもできますが、刺激の多い部位に多く、口唇や舌などの粘膜にできることもあります。
激しいときは手の平よりも大きく広がり、かゆみも激しくなります。慢性化して1年~10数年にわたって反復することもあります。
反復する人は、その原因を明らかにして、処方を受けることが必要です。
■ツボ治療法
背中の大椎、肺兪、肝愈、腰の腎兪、大腸兪、胸の膻中、腹部の中脘、関元、手首の陽池などがポイントになります。マッサージや指圧は体質改善としてはよいのですが、より効果が期待できるのは、鍼灸治療です。
■民間薬
①サクラ
サクラの生の葉15枚ぐらいを細切りにして、200mlの水で半量になるまで煎じ、その汁を1日分として、3回に分けて食前に飲 みます。また、サクラの木の内皮を煎じて、1日に3回ぐらい飲みます。
②シソ
サバやイワシなどの魚によるジンマシンによく用いられます。
用い方は、シソの葉を生業で食べるか、乾燥させたもの10gを1日分として、煎じて、その汁を飲みます。
③黒ゴマ
黒ゴマを軟かく妙ってこれを粉末にし、蜂蜜を加えて、これを1日2回飲むか、服用時に、さらに黒ゴマと日本酒と水を少量加え、15分ほど放置してから飲みます。なるべく空腹時に飲む方がよいようです。
④コンニャク
食べると有効です。
 |

|
神経痛
神経痛は寒冷、湿潤、感染、中毒、整形外科的病変、腫瘍などがきっかけとなって、末梢神経の走る経路にそって起こる痛みが特徴です。
そのほかに、痛みが発作性に起こり、発作と発作の間にまったく痛みがない、痛みのある神経を調べても病理解剖学的な変化が認められない、などいくつかの特徴があります。したがって、神経痛は症候名で病名ではありません。
神経痛で比較的多いものに、三叉神経痛、肋間神経痛、坐骨神経痛があります。
神経痛は青年から中年の人に多く、女性よりも男性のほうが多くかかります。
神経痛の治療には、まず原因をはっきりさせることが先決です。鍼灸、マッサージ、指圧など東洋医学的治療はたいへん効果があります。
■ツボ治療法
神経痛の痛みは、患者が痛みのある場所を正確に示し、そこはまた神経の走る場所と実によく一致しています。したがって、神経の走行にそって、その皮膚の上を指で押していけば圧痛点が必ずあります。鍼治療の場合は、その圧痛点に刺鍼するか、その上方の部に刺鍼します。
このように、疾患の部位によって阿是穴あるいは正穴を治療するとともに、腰の三焦兪、背中の厥陰兪、手の合谷、曲池、手三里、足の三里などにも施術します。
■民間薬
①ヨモギ風呂
よく全身が温まります。また、その成分の働きで神経痛の痛みも和らぎます。生の葉ならば100g、乾燥したものなら50gを木綿袋に入れて風呂に入れ、ぬるめのお湯にゆっくりつかるようにします。
②カボチャ
肋間神経痛に向いています。カボチャを煮てドロドロにしたもので、患部を湿布します。消炎、止痛効果があります。
③オガクズ
米ぬか6対4の割合で混ぜ、袋状の腹巻きを作ってその中に入れます。この腹巻のオガクズが入っているほうを、へその後ろにあてておきます。1カ月くらい続けましょう。
④ビワの葉
エキスを痛む箇所に1日3回塗る痛と、次第に効きめが現われてきます。
⑤サボテン
サボテンをすりおろして、痛むところに貼ると、痛みがやわらいできます。
神経症
いつも頭が重く憂鬱で気力がない。仕事ができないほどでないが、気分が乗らず、ちょっとしたことでいらいらする。眠れない。病院に行っても特別に異常がないと言われる。このような症状で悩む人が多いものです。
昔は神経衰弱といいましたが、最近では心身症とか神経症がこれに当たります。
原因は心理的なものですから、治療は心理療法がもっともよいのですが、なかなか治りにくいのです。神経症になりやすい人は、弱気で、遠慮、気がねの気持ちが強く、自分を抑え、がまんしがちの人に多くみられます。
心の病気に共通している症状は、大体には不眠です。熟睡するためには、自律神経が安定しなければなりません。
■ツボ治療法
後ろ首の天柱、風池、瘂門、背中の厥陰兪、心兪、三焦兪、胸腹の膻中、巨闕、手の郄門、 神門などが重要な治療穴です。また足の三里、 湧泉などもポイントになります。
また、旅行や山登り、スポーツなどで気分転 換をはかることも大切です。
■民間薬
①シソの葉
よく洗って、生のまま食べます。不安感、イライラ、不眠などに効果があります。
②酢卵
卵をよく洗って、殻ごと酢につけます。酢卵には、卵の殻の成分が溶け込んでいますの で、カルシウムがたっぷり含まれています。このカルシウムが神経のイライラを鎮めてくれますので、神経症の人には有効です。
③サンショウ
サンショウは昔から邪気を払い、無病息災をもたらす木で、福の木といわれています。サンショウの実をすり鉢に入れてすりつぶし、さんしょうの実とおなじくらいの米の粉をまぜ、果粒大にしたものを1日5~10粒飲みます。常飲すると、サンショウには精神状態を安定させる効果があります。
④ホウレンソウ
めまいや頭痛の症状には、ホウレンソウを常食するとよいでしょう。
 |

|
小児ゼンソク
一般に小児ゼンソクという場合、ゼンソク様(性)気管支炎と、気管支ゼンソクとがあります。ゼンソク様気管支炎は、カゼをひくとゼイゼイいって呼吸が苦しくなるもので、3歳ぐらいまでに治ってしまいます。
これに対して、気管支ゼンソクは、発作的に呼吸困難を繰り返す病気で、乳児には少なく、3~4歳ごろから多くなります。気管支ゼンソクは、アレルギー性の疾患と考えられます。家の中のほこり、花粉、カビ、繊維などに体が過敏になっており、そのために発作が起こるものと思われます。
治療に際しては、まず何が原因となってアレルギー反応が起きているのかをさがすことがたいせつです。
■ツボ治療法
小児ゼンソクのポイントとなるツボは、図の大椎というツボです。
片手でひたいを押さえ、片手でぼんのくぼから軽く指先で、くびの骨を上から順に押さえていくと、この大椎のところにとくに強い圧痛を覚えます。
小児ゼンソクは、このツボを中心に、背中の肺兪、腎兪、のど元の天突、胸の中府などを用います。
刺激の方法としては、仁丹粒か米粒をツボに当ててバンソウコウで止める、一種の圧刺激が効果的です。持続的な圧を加えることにより、発作を軽くし症状をやわらげることができます。
■民間薬
①ジャガイモ
よく洗って皮ごと四つ切りから 八つ切りにして、水をたっぷり入れ、弱火でぐつぐつと煮立てます。そしてスープを作り、湯飲み茶わんに1杯ずつ飲ませます。体力をつけ、 発作をしずめる効果があります。
②ニンニク
1個の外皮と薄皮をむいて、アルミホイルに包み、蒸し焼きにします。それを1日3回に分けて、ハチミツをかけて与えます。ただ1日1個以上は強すぎるので、それ以上与えないように注意を要します。
③松やに
1回にアズキ1粒ほどの量を、よくかませ、服用させます。1日3回与えます。ただし、胃腸の丈夫な子に用います。
④オオバコ
全草を陰干しにしたもの10gほどを300mlの水で半量に煎じ詰め、1日3回、空腹 時に飲ませます。小児虛弱体質
虚弱体質とは、体質が生理的に不安定で、刺激に対して、ふつうの子どもより過敏に反応しやすいものをいいます。いわゆるひ弱な子どものことで、腺病質などとも呼ばれることもあります。また年齢層によって、乳児期なら滲出性体質、幼児期ならリンパ性体質などといわれることもあります。
こうした虚弱児の体質改善には、現代医学はなかなか決め手はありませんが、ツボ刺激はたいへん効果があります。
■ツボ治療法
背中の大椎、身柱、膈兪、肝散、脾兪、腰の腎兪、命門、腹部の中脘、水分、胃兪、天枢、手の孔最、足の足三里などがよく活用されます。
これらのツボには、小児鍼を用いて、鍼を刺さずに、鍼先で軽くツボを刺激するだけで、効果があります。灸の場合は、10歳未満の子どもには、もめん糸大のできるだけ小さい灸をすえます。また、知熱灸や温灸も有効です。
温灸の場合は、神闕(しんけつ)に治療を施すと元気が出てきます。つまり、へそ灸です。さらに、各ツボに磁気粒を貼っておくのもよい方法です。
■民間薬
①セロリ
ビタミンB2をとくに多く含み、そのほかB1、C、メチオニン、グルタミン酸、鉄などを含んでいますので、健胃、強壮、補血の効果がすぐれ、常食させれば、体質改善にもなります。
②カボチャ
カボチャは体を温める働きがあって、虚弱体質を強くします。
③ギンナン
少しずつ与えると、虚弱体質が改善できます。ただし、いちどに多量に与えると胃腸を害するので、注意を要します。
④ヨモギ
葉をすりつぶして小麦粉とねり合せ、団子にして蒸します。それに黒砂糖かハチミツをつけて与えます。
⑤ニンニク
皮が黒くなるまで焼いて食べさせます。だいたい小片1個から大片1個までを、1日3回に分けて、食後に食べさせてください。
 |

|
腎臟病
腎臓病の中で代表的なものは、慢性腎炎とネフローゼ症候群です。慢性腎炎は、10~40代の間に多くみられ、大多数が自覚症状がなく、入社時の検診や定期検診、あるいは風邪や妊娠時などに偶然タンパク尿を発見され、気づくことが少なくありません。進行すると体がだるく、むくみとか高血圧、心疾患などが生じて、治療はなかなかやっかいです。
ネフローゼ症候群というのは、独立した一つの病名ではなく、①高度のタンパク尿、②低タンパク血症、③高脂血症、④全身性のむくみ、の4つを主な症状とするものにつけられた広い呼び名です。
ツボ治療を行うと、腎臓病の諸症状が軽くなり、体調がよくなってきます。
■ツボ治療法
背中の肝兪、腰の腎兪、体の前面では水分、 肓兪、気海、足の裏の湧泉、ひじの曲池などで、とくに腎兪と水分は腎臓病の場合の特効穴といえます。また、腎臓病は長い経過をとることが多いので、日常生活と食事に気を配り、風邪その他の感染防止に努め、血圧の上昇を防ぐようにします。
■民間薬
①スイカ
生のまま食べると、尿量をふやし、むくみをとります。カリウムと果糖の働きが腎臓病一般に効果があります。
②ニンジン
すりおろして布でしぼり、その汁をさかずき1杯ぐらいずつ、1日3回食間に飲みます。
③アズキ
煮て汁をとり、湯飲み茶わんに1杯ぐらいずつ、1日3回食間に飲みます。
④トウモロコシ
トウモロコシの毛を1日量5 ~10gを煎じて飲むと、効きます。
⑤ミョウガ
根茎10gを540mlの水で半量にせんじ詰め、1日数回に分けて飲みます。
⑥クロマメ
煎じて1日数回飲みます。
⑦ハトムギ
30gを煎じて、お茶がわりに飲みます。
⑧キュウリ
つぶして汁をとり、飲みます。
心臓神経症
ノイローゼの一種で、心臓に関係のあるいろいろの訴えがあっても、心臓には何の異常のない場合を心臓神経症といいます。
症状は心悸亢進、胸部の圧迫感、呼吸困難、不安感、心臓部の疼痛、頭痛、めまい、冷や汗、しびれ感、四肢の冷感、脱力感、腹痛、便秘など、その訴えがあっても統一のないのが特徴です。
原因は精神の過労、劣等感、満たされない欲望感、夫婦関係で交接時間が短く、性欲を十分 に満足させられない場合も原因になります。心臓神経症は重病人ではないのですから、床になどつかないで元気に働くことです。
ツボ治療法に心臓病につながる危険がない動悸に対して、たいへんあります。
■ツボ治療法
後ろ首の天柱、背中の厥陰兪、心兪、胸の膻中、腹部の巨闕、手の郄門、少衝、少沢、神門などといったツボがポイントになります。
■民間薬
①卵油
突然胸苦しさをおぼえたら卵の黄身の黒焼きを作っておいて、具合いの悪いときに用います。卵30個の黄身を鍋でじっくり炒きます。焦げつかないようにかきまぜていますと、そのうちに真っ黒い油のようなものができますから、それを広口びんにとって保存しておきます。用量は1回につき、さかずき1杯です。
②しそ
しその葉や実は、精神を安定させる作用があります。
③ツユクサ
花茎根まで細かく刻み、干したもの15gを1日の量として約500mlの水で半分になるまで煮つめ、毎食前30分前に飲みます。
④クルミ、黒ゴマ、クワの葉
夜眠れない時、よく夢を見る、神経が弱っている時などは、各30gをつぶしてドロドロにした物を1回9gずつ分けて飲みます。

| す |
 |

|
頭重・頭痛
頭痛はいろいろな病気の前ぶれであったり、 慢性病の症状の一つとしても起こりますが、時にはとくに病気がなくとも、疲れたり、気候や気象の変わりめ、女性では生理時、また自律神経の失調やアレルギー体質の人に見られます。血管性、筋収縮性、心因性の三つに頭痛を分けます。このほか頭の皮膚にめぐる神経の痛みでも頭痛は起こります。
頭痛・頭重は、原因がはっきりしていれば、医者にかかってその原因をとり除く治療をすればよいのですが、原因をとり除く治療に加えて、補助手段としてツボ治療は効果をあげることができます。また、原因のはっきりしない頭痛・頭重はとくに治療がよいものです。
■ツボ治療法
ツボ治療としては、頭のてっぺんの百会、米嚙、後頭、髪の生え際の天柱。これは頭痛、頭重に大切なツボです。肩こりを伴なう時には、肩の中央の肩井が効果があります。お腹の不快感を伴う時には鳩尾とおへその中間の中脘、そして手の合谷。このツボも、頭痛や頭重に大変効果のあるツボです。
■民間薬
①ダイコン
皮ごとすりおろしてしぼった汁を前額部に塗り、冷やします。
②リンゴ
洗って皮とともにおろし、和紙の上にのばし、ひたいに貼りつけます。また、直接頭にすり込んでも効果があります。
③しょうが油
ヒネショウガをすりおろしてしぼった汁と、純良のごま油を等分にまぜたものを、こめかみにすり込みます。
④コマツナ
青いひたいに貼りつけます。葉がしんなりとしてきたら、とりかえます。
⑤タマネギ
すりおろしてしばった汁を、小さかずきに1杯飲みます。
⑥くず湯
くず粉少量を水にといて煮て、くず湯を作り、茶わん1杯飲みます。
⑦キク
黄色の花を1日量5gほど煎じて飲みます。

| せ |
 |

|
生理痛・生理不順
生理痛・生理不順は精神的要素やホルモンのバランスが関係すると考えられています。 これは女性の生理が左右大脳半球の間にある間脳の影響を受けることを示しています。間脳は情緒の働きを支配するものですが、排卵作用をつかさどる下垂体前葉から出るホルモンも支配しています。このホルモンの分泌が順調でないと、卵巣から卵子が正常に排卵されないことになります。ホルモンの分泌が異常になると生理周期が乱れ、生理がいつ起こるか予測できなくなります。
原因となっているホルモン分泌の異常を正すとともに、体に十分栄養をつけて、規則正しい睡眠をとるといった精神、肉体両面の安定につとめるようにしましょう。
■ツボ治療法
腰の腎兪、同時に骨盤部の大腸兪、膀胱兪、上髎、胞肓、さらに下腹部の大巨、関元、中極、水道、足の血海、三陰交などがポイントになります。
生理痛、生理不順は鍼灸療法がたいへんよく効きます。ただし、2~3ヵ月は続けないと効果が上がりませんから、ねばり強く治療したいものです。
■民間薬
①サフラン・ハトムギ
煎じてお茶がわりに飲むと体が温まり、荒れ症の人は肌もきれいになり、生理も順調になります。
②モモ
1日に種子5~10g煎じて飲みます。葉も1回に3~6g煎じて飲んでも、月経時の腹痛、腰痛を治す効果があります。
③アケビ
アケビのツル20gを1日量として飲むと、生理不順によいでしょう。
④ショウブ湯
生理痛、生理不順に向いています。ショウブの葉を一つかみ湯舟に入れ、入浴します。
⑤クマ笹風呂
葉茎を、大きななべにゆでて、その汁を風呂に入れ、布袋にクマ笹を入れて風呂に浮かして入浴します。
⑥ヨモギ
薬を陰干しにしたもの10gを煎じて飲みます。
精力減退
精力減退は、性欲があっても肝心なものが役にたたないインポテンツであるといいますと、ちょっといいすぎになりますが、齢を取ってきますと、性欲が落ちて勃起力が減退したり、回数が減ったということもあります。
また、神経過敏な人が、仕事の負担などで疲労、代謝障害、内臓疾患、薬剤中毒の乱用が原因になることもあります。過度の心配、悲観は禁物です。インポテンツは、原因の大半は精神的なものと考えられています。
東洋医学では、生まれながらに人間が持っているエネルギーと、生まれたあとに人間が自然界からとり入れていくエネルギーを、いかに順調に保ち、使っていくかということにポイントをおいて治療します。
■ツボ治療法
下腹部の関元、中極、大赫、へその両脇の肓兪、腰背部の肝兪、胃兪、三焦兪、腎兪、膀胱兪、手の陽池、足の三陰交、湧泉などがポイントになります。
東洋医学では精力の減退したことを「腎虚」といいますが、治療するとき、腎虚の証を発見するツボとして肓孤と湧泉が重要です。この二つのツボを親指か人さし指でぐっと押してみて、 かたいしこりとともに、ウッとうなるような痛みがあれば、精力減退の証拠です。
■民間薬
①クマ笹
エキスは昔から強壮強精の妙薬として知られています。
②ニンニクエキス
ニンニクの強精効果をよく知られています。ニンニク10粒をすりおろし、日本酒1升の中に入れ、2カ月ほど経過したら ニンニクエキスができます。これを毎日茶さじ半分ほど飲みます。
③イカリソウ
イカリ草は中国名を淫羊羹というほど、精力増強に効果があります。乾燥したイカリソウの葉20gを1日量として、水500mlで 煎じて、1日3回飲みます。気長に飲み続けましょう。
④カヤの実
カヤの実を1日数個ずつ食べると、精力増強に役立ちます。またカヤの実と黒ゴマとすりつぶし、それをまぜ、食べるもよいでしょう。

| た |
 |

|
脱毛症
正常な人でも毎日50本以上の毛が自然脱毛し、新しい毛髪に生え変わっているといわれます。しかし、脱毛が著しくなると、結果としてはげになります。
最も多いのは、円形脱毛症と呼ばれるもので、ある日突然、前触れもなく頭髪が円形に抜けてきて、十円玉ぐらいの大きさになると脱毛の範囲が広がらなくなります。この円形の脱毛斑は1個だけのこともありますが、ときに数を増し、隣の脱毛斑とくっついて、比較的短時日の間に広く脱毛する場合もあります。
脱毛の原因については、自律神経失調によるのではないかといわれますが、はっきりしたことはわかっていません。精神的なストレスなどが、皮膚の自律神経になんらかの形で影響しているためかもしれません。再発しやすいので注意が必要です。
■ツボ刺激法
頭の百会、後ろ首の天柱、背中の大椎、肺兪、腰の腎兪、胸の中府、おなかの中脘、関元、手の合谷、孔最、太渕がポイントになります。
また前記のツボの中で、百会、天柱、腎兪、中脘、関元、合谷はとくに脱毛の予防としても効果のあるツボです。
■民間薬
①トウガラシチンキ
昔から脱毛症に用いられています。作りかたは、薬用アルコール100mlに、トウガラシの実10gを入れて1週間ほどおいてから、これを頭部にすりこみ、マッサージをします。
②アオギリ
果汁を黒焼きにし、それを粉末にして少量のゴマ油で練ります。毎日数回根気よく続けることが大切です。また、生の樹皮をすりつぶした汁をヘアートニックの代わりに用いると発毛が促進し、髪のつやをよくする効果がります。
③ゴマ
常食すると、抜け毛を防ぎ、毛髪を濃くします。
④コンブ
ヨードに富み、毛髪を濃くする効果があります。ヒジキ、ワカメも同様に常食すると有効です。
胆石症
胆石症は胆嚢や胆管の中に石ができる病気で す。胆石ができる原因には、代謝異常・胆汁のうっ滞・胆囊炎などがあげられますが、胆石の組成により、コレステリン系胆石、ビリルビン系胆石、その他の胆石に大別されます。美食家、大食家、肥満者に多くみられますので、動物性脂肪の取りすぎも原因だと思われます。
症状は腹痛、黄胆、発熱、悪心、吸吐などですが、痛みは背部に放散性を伴う上腹部の発作性激痛で、胆石貼痛といっています。胆道のものは胆囊から流れ出したものです。 痛みが強いときは安静にし、症状がおさまったら胆石に対して処置を考えなければなりませんが、一般的には便通をよくし、脂肪の摂取を避けることが重要です。
■ツボ治療法
背中の肝兪、胆兪、脾兪、胃兪、のどの気舎、おなかの中脘、天枢、足の築賓が主要なツボです。とくに築賓は解毒のツボとされ、重要視されています。また、手の三里、内関を治療すると、胆石の痛みが軽くなります。
■民間薬
①ハトムギ
実を穀つきのまま20gを600mlの水で半量になるまで煎じ、これをお茶がわりに飲 みます。ハトムギは胆石溶解作用やイボとりの妙薬といった働きもあるといわれています。
②ナズナ
ナズナは別名ペンペン草ともいわれています。実のついているものを根ごと採って陰干しにし、1~5gを煎じ、1日分として、 3回に分けて飲みます。ナズナは胆石症のほか、 高血圧にも効果があるといわれています。
③ヒキオコシ
葉と茎10~15gを土瓶に入れ、 水500mlで半分量になるまで煎じつめ、これを1 日3回に分けて飲みます。昔から腹痛や胆石の痛み止めに使われております。
④コンニャク
胆石を排出する働きがあるといわれています。適当に料理して、毎日食べてください。

| ち |
 |

|
中耳炎
中耳炎は細菌によって炎症を起こす病気です。
中耳炎には上気道の急性炎症に続発する急性単純性中耳炎、病原菌が耳管から中耳の鼓室に感染を起こす急性化膿性中耳炎、ジフテリア菌が耳管を経て鼓室に二次的に起こすジフテリア性中耳炎、麻疹によって起こる麻疹性中耳炎、主として血行性感染で起こる猩紅熱性中耳炎、化膿菌や腸チフス菌等によって起こる腸チフス中耳炎等があります。
いちばん多いのは、かぜに続いて起こる中耳炎です。
高熱が出て、食欲がなくなり、激しい疼痛がおこり、耳が聞こえなくなったり、耳だれになったりします。再発して慢性になりやすいので、 専門的早期治療が必要です。
■ツボ治療法
痛むときは、耳のまわりの翳風、耳門、完骨、それに加えて、手の合谷を治療します。また、手の三里、腰の腎兪、へその両側の骨、内くるぶしの復溜と太谿を治療すると、より効果が上がります。
■民間薬
①ゴボウ
昔はゴボウをつぶして、その汁を耳の中に入れたそうです。中耳炎の特効薬とされていますので、つぶしたものをガーゼなどにのばして、患部の皮膚に貼ります。
②アロエ
アロエをすりおろし、これをていねいにしぼり、1日3回、2~3滴患部の外耳孔にたらすか、または綿棒につけてふきます。
③いも薬
サトイモをおろし金ですって小麦粉とショウガ一片をすりおろして加え、よくまぜます。それを布にのばし、痛む葺の外部周辺にべったりと貼ります。熱があるときは、3~4時間ごとに貼りかえます。
④梅干し
種子を除き、皮と果肉を平らに広げ、皮のほうを上にして果肉を痛む耳の周囲の皮膚にべったりと貼りつけます。梅干しが乾いたら、とりかえます。

| つ |
 |

|
椎間板ヘルニア
ほとんどが急性に起こり、痛みで、立とうとしても立てなかったり、急に動けなかったりします。原因としては、椎間板がしだいに水分を失うなどのいわゆる変性を起こして、十分な負担能力がなくなっているところに、なんらかの拍子に線維輪の弱い部分から髄核が飛び出して椎間板ヘルニアの正体です。
椎間板ヘルニアは若年者腰痛の主因で、若い人のギックリ腰といわれるものは椎間板ヘルニアが多いのです。
初めはしばらくは急性症状が強くても、間もなく症状が緩和することが多いので、重症のものでなければ、手術をしなくてもよいのです。
また水泳をすると、椎間板へルニアの治療にもなりますし、予防としても非常に役立ちます。
■ツボ治療法
腰の腎兪、大腸兪、関元兪、おなかの中脘、足の承山、足三里、解谿などがポイントになるツボです。いずれにしても、まずギクッと痛んだら、まず動かずに、固い布団の上で安静にして、それから治療を受けるようにします。
■民間薬
②サボテン
サボテンの表面をナイフで傷つけ、にじみ出てきた汁を布につけ、湿布します。
②ハス
葉を乾燥させたもの10~15gを400mlの水で半量まで煎じ、1日3回に分けて食前に飲みます。
③ヨモギ
ヨモギの葉を乾燥させたもの40gと ニワトコの茎40gを布袋に入れ、これを浮かべた湯に入ります。
④マタタビ
果実を煎じて飲み、さらにツルや葉を湯に入れ入浴するとよいでしょう。とくに女性の腰痛によいといわれます。
⑤ドクダミ
乾燥したものなら葉を100~200g、生ならば全草を適当量採取して、布袋に入れて せんじます。せんじ汁を湯に加えて入浴します。
⑥青汁
ダイコンの葉、カキの葉、ハコベ、ニワトコの葉を合わせて青汁を作り、常用します。
痛風
痛風は、本来容易に腎臓から排泄されるはずの尿酸が十分排泄されないで、その血中濃度が高くなることが原因で起こる病気です。これは糖尿病と同じく、物質代謝障害から起こるものです。尿酸が血中に過剰に蓄積されますと、針状の結晶の束をつくって、関節などに沈着します。その結果、関節などが激しく痛み出すのです。
痛風は「帝王病」ともいわれ、美食家、大酒家に多く、肥満している人にできやすいようです。患者の90%は男性で、40歳以上の人に多くみられます。普通は足の親指の付け根が急に痛みだすことで始まります。痛みは激烈で、歩くことも困難になります。
ツボ治療は痛みを瞬時にとることはできませんが、激痛をやわらげてくれます。
■ツボ治療法
背中の脾兪、三焦兪、腰の腎兪、命門、おなかの中脘、肓兪、手の陽池、足の築賓、三陰交、 太谿などがポイントになります。
鍼灸の刺激は、細胞に損傷をあたえるため、白血球が増加して、食菌作用が行われ、また血行をよくして、痛風によく効きます。
■民間薬
①カラシ泥
カラシ粉とうどん粉を同量まぜ合わせ、ぬるま湯でといて和紙かガーゼに適当な厚さにのばし、これを患部に当てます。1日1 回取り替えます。カラシ泥は刺激が強いので、皮膚にかぶれが起こるようでしたら、早く取り、時間をおいて湿布するようにします。
②クチナシ
クチナシの実を煎じて飲みます。
③ヒノキ
ヒノキの節10~20gを1日量とし、煎じて飲みます。
④スイカズラ
花・茎・葉を10mgとニワトコ10gを1日分とし、煎じて飲みます。
⑤マタタビ
実を1日分15g煎じて飲みます。マタタビの実を2~3ヵ月酒に漬け、マタタビ酒として飲みます。
⑥キク
乾燥した花を1日5g、煎じて飲みます
 |
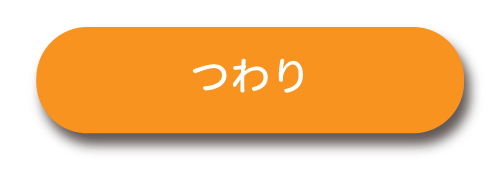
|
疲れ目
<疲れ目 (眼精疲労)は、単に目の疲労というよりも全身疲労の一つの症状ともいえます。目がしぶい、まぶしい、物が二重に見える、目の奥が痛むなど、症状はいろいろです。また、全身的には、頭痛、頭重感、めまい、肩こり、吐きけ、胃のもたれなどを訴えることが少なくありません。原因としては、多くは肉体的・精神的疲労、睡眠不足などがあげられます。また、眼鏡の度が合っていないとか、遠視、乱視、老眼の初期段階などでも眼精疲労がおこります。全身の疲労、目の病気なども原因になります。
<したがって、目の疲れが頑固に続くようなら専門医に診てもらったほうがよく、特に注意が必要なのは、緑内障の初期症状や脳腫瘍、低血圧症、貧血などです。
<■ツボ治療法
<疲れ目によく効くツボは、まゆ毛の内側の攅竹、外側の絲竹空、目がしら側の睛明、目尻側の瞳子膠の4つです。さらに腰の腎兪にも治療 を加えると、いっそう効果があります。
<また家庭では冷たいタオルを両目に当てて冷 湿布したあと、瞼の上から両手のひらの腹で軽く眼球を押さえるようにして、左右になでるとよいでしょう。疲れ目がひどくなり、頭痛や肩こりなどを伴なってきましたら、後ろ首の天柱、風池を矢印の方向にもみほぐします。目の奥に痛みを感じるときは、天柱、風池を中心のほうから耳の後ろへ親指の腹でもみほぐし、3~4 回繰り返します。
<■民間薬
<①ピーマン
<目を健康にするために必要なビタミンA・Cが豊富に含まれていますので、常食すると視力を強化し、眼精疲労を治す効果があります。
<②ニンジン
<すりおろして汁をしぼり、さかずきに1杯ぐらいずつ、1日3回飲みます。毎日つづけていると、目の疲れがとれてきます。
<③ウナギ
<ウナギにはビタミンAが多量に含まれているので、目の疲れを回復させる働きがあります。とくにヤツメウナギは、ビタミンAの含有量が普通のウナギの8倍以上もありますの で、たいへん効果的です。
<④ゴマ
<常食していると、視力が増進し、疲れ目を治します。また、1日5~10gほど煎じて飲んでも有効です。
<⑤メハジキ
<種子を2~6g煎じて飲みます。
つわり
つわりは妊婦にあらわれる消化器系統の症状であって、病気ではありません。
随伴症状として、吐き気、嘔吐、食欲不振、頭痛、めまい、便秘、全身倦怠などを伴うこともあります。唾液が多く分泌されたり、飲食物に対する好みが変って、すっぱいものが欲しくなることもあります。つわりは早朝空腹時に著明に出ることもあり、この場合は早朝嘔吐といいます。
また、生来神経質な人につわりが重くなる傾向がみられ、心理的なストレスのある人が重症になりやすいという、心身症としての性格も多分に認められます。
どの程度の症状ならどういう手当てをすべきかは、専門医の指示に従いましょう。
■ツボ治療法
ツボ治療法は、それぞれの症状をとるための 対症療法として、また全身のバランスをととのえる意味で用います。
後ろ首の天柱、肩の肩井、腰背部の曲垣、肝兪、脾兪、胃兪、横首の扶突、天鼎、手の内関、足の地機、築賓、三陰交、梁丘、三里などのツボから選んで治療します。
■民間薬
①ヒネショウガ
吐き気のある場合によく用いられます。用い方はヒネショウガを薄く切って、少し火で焙ったものを口に含んでいるだけですが、効果があります。
②ハス
日干しにしたハス10gを1日量として、これをすりおろし、等量の水を加えて10分ぐらい煎じます。この煎じ汁を1日3~4回、盃に1杯ずつ飲みます。
③クサボケ
乾燥させた果実を輪切りにしたもの15gを1日量とし、450mlの水で半量になるまで煎じます。煎じる時間は30~40分です。これを冷やして、1日数回に分けて飲みます。
④大根おろし
しょうゆをかけて常食します。
なお、つわりだからといってゴロゴロ寝ていたら、かえってよくありません。つとめて働くことが大切です。

| て |
 |

|
低血圧症
一般に最大血圧が3以下の場合を低血圧といいます。
低血圧には本態性低血圧、二次性低血圧、起立性低血圧の3種類に大別されますが、最も多くみられるのが本態性低血圧で、体質的なものはいわれているものの、原因ははっきりわかりません。
最も多い本態性低血圧は、背が高くてやせ型の人に多く、主な自覚症状は、疲れやすい、飽きっぽい、体がだるい、食欲がない、めまい、耳鳴りがする、手足が冷えやすい、便秘する、生理が不順、寝覚めが悪い、などといったもの です。
やせ型の若い女性によくみられるめまい、立ちくらみは、起立性低血圧が多いといわれます。
■ツボ治療法
頭の百会、後ろ首の天社、腰背部では肩井、心兪、腎兪、腹部では肓兪、大巨、手では陽谿、太渕が主要な治療ツボです。
■民間薬
①リンゴ
生のままか、蒸して常食していると血圧が正常に復します。
②キュウリ
生食が有効です。
③ニラ
ニラは血液の循環をよくし、体をあたためる効果があるので、常食します。
④ニンジン
すりおろして布でしぼった汁を、さかずき1~2杯、毎食時にとります。
⑤アズキ
砂糖で味つけせずに、ゆでて茶わん1杯ぐらい食べると、ビタミンB1や鉄分がとれて有効です。
⑥キャベツ
キャベツを食べると効果があります。
⑦ハチミツ
大さじ一杯を1カップの水か湯にとかして毎日飲みます。
⑧コンフリー
おひたしや天ぷらにして食べます。
⑨ヨモギ
葉を乾燥させたものを20gを煎じて飲みます。体が温まります。
次のような乾布まさつ、冷水まさつ、あるいは腹筋運動も、低血圧体質を改善してくれます。気長に行いましょう。
●乾布まさつ
日本手ぬぐいか浴用タオルを使い、毎朝全身をまさつします。①左手くびからひじへ。②左ひじから肩へ。③右手も同様にこすり上げる。④胸のまさつは側方から中央へ。⑤腹部は側方から中央へと、下方から上方へと、二とおり行います。まず、上腹部を左側から中央へ、次に右側から、さらに下腹部を下方から上方へこすり上げます。⑥背中は乾布をたすきがけのようにし、まんべんなく行います。⑦腰と尻。⑧足は下から上へこすり上げます。まず足くびから膝へ、膝からももへ。左足から始めて右足に移ります。
まさつの方向は、心臓に向かって行いますが、このように血液が心臓に戻る静脈の走行に沿ってまさつすることは、血行を盛んにするうえで、より効果的です。
●冷水まさつ
日本手ぬぐいか浴用タオルを冷水につけて、かたくしぼります。方法は乾布まさつと同様ですが、初めに乾布まさつで皮膚を慣らしてから移ると楽にできます。
●腹筋運動
低血圧の克服に効果があります。 ①腰をおろし、たんすの下の段の引き出しを少し引き出し、その下に両足の先をかけます。両足をのばし、くびの後ろに両手をあてて上体を静かに倒し、再び起き上がります。
もう一つの方法は、
①床にあおむけに寝て、両手を後頭部に当てます。②両足をそろえ、床と垂直になるまでもち上げます。足を伸ばしたまま床とすれすれになるまで静かにおろし、再び上げます。何度も繰り返します。

| と |
 |

|
動悸がする
健康な人でも、激しく運動したり、緊張したりすると、胸がドキドキします。これは正常な生理現象ですから、心配することはありません。夜寝ている時、突然心臓がドキドキして目がさめ、不安で眠れなくなり、そのうち心臓のあたりが痛くなってきて、息切れし、冷や汗までが出てきます。 しかし心臓自体には何の支障があるわけではないので、別名心臓神経症といっています。脈拍は100以上にもなります。
また原因としては、心臓病、高血圧、低血圧でも動悸を感じることがあります。貧血ですと、血液中の酸素の量が足りないので多くの血液を送り出そうと、心臓の拍動が速くなることがあります。
■ツボ治療法
背中の厥陰兪、心兪、胸腹部の膻中、巨闕、手の郄門、神門といったツボがポイントになります。とくに胸のまん中にある膻中は、心臓発作の際に重要なツボです。また動悸の治療には、手の部門も重要な役割を果たします。
■民間薬
①クマ笹風呂 クマ笹を取ってきて、大きななべか釜に入れてゆで、その汁を風呂に入れます。また木綿袋にクマ笹を入れて、風呂に浮かして、ぬるま湯で入浴すること。お湯を抜かないで、3回くらい使います。
②シソ
葉を乾燥させて、茶として飲みます。
③ハス
ハスの実を毎日食べると、心臓が弱く、神経質な人にはよいでしょう。
④アジサイ
中高年になると、これといった病気でもないのにちょっと動いただけで息切れがして胸が苦しくなる、いわゆる動悸がする人が多くなります。こうした症状にはアジサイの葉を陰干しにしたものを、1日4g煎じて朝夕に飲むと効果があります。
⑤クチナシ
実を1日量として、5~10個煎じて毎日飲みます。
糖尿病
糖尿病は、膵臓から分泌されるインシュリンの量が少ないためにおきる代謝の障害です。インシュリンが不足すると、我々が活動するための燃料としてのブドウ糖が、体内で燃えなくなってしまいます。ブドウ糖が燃えないと、血液の中の糖が高くなり(高血糖)、多くの障害が起こるわけです。糖尿病の自覚症状で最も多いのは頻尿、多尿ですが、こわいのは血管の動脈硬化や血行障害が起こりやすくなることです。心筋梗塞、脳血栓、白内障、腎盂炎、手足のしびれなどです。またインポテンツ、おでき、かゆみなどの合併症も出てきます。
肥満、美食は糖尿病の誘因となります。尿に特有な臭いがしたり、多尿、口渇が起こったら注意しましょう。
■ツボ治療法
背中の肺兪、脾兪、胃兪、腰の腎兪、腹部の天枢、肓兪、大巨、手の内関、手三里、足の三里、三陰交、地機などがよく使われます。
■民間薬
①カボチャ
常食すると膵臓の働きをよくするので有効です。カボチャをそのまま蒸すか、よいダシで味つけして煮るかします。主食の代用とすればよく、緑葉野菜を添えて食べましょう。
②キャベツ
ビタミンB1・B2・C・K、カルシウムをともに相当量含み、糖分の分解を円滑にしますから、糖尿病を好転させることができます。
③シイタケ
ビタミンDを多く含み、体内の糖分の燃焼を盛んにする働きがあります。いろいろに料理して食べます。
④とうふ
常食すると有効です。植物性タンパク質に富み、カルシウム、ビタミンB1・B2も含まれますので、糖分の分解を円滑にします。
⑤アズキとこんぶ
いっしょに煮て、食事ごとに食べます。
| に |
 |

|
尿路結石
尿路結石は、泌尿器系の器官にできる結石です。尿路結石も発生する器官によって、腎臓結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石などといいます。とにかく、尿路の中に結石ができ、このため尿路がつまったり、結石が尿路にひっかかったりして起こる障害が尿路結石です。
症状は横腹から背中にかけて痛み、しばしば下腹部に広がります。また、悪心、嘔吐、尿量の少ない頻尿、血尿なども伴います。
激痛のときは、石が尿管に引っかかっているときですから、尿が減少して濃くならないように水分を多くとる努力をして、結石を膀胱に下降させるようにします。
尿路結石は、20代から40代の男性に多くみられます。
■ツボ治療法
ツボは、利尿と腰や下腹部の痛みを抑えることを目的に選びます。腰では腎兪、膀胱兪、下腹部では関元、中極と水道、それにへその上の水分、さらに第5腰椎の下かたわらの大腸兪、足の湧泉などが中心になります。
また、入浴したり、ホカロンやカイロで体を温めると尿管が広がり、排尿も楽になり、石が排泄されやすくなります。
■民間薬
①タケノコやホウレンソウ
よくゆで、そのゆで湯を捨てずに飲みます。
②カッセキ(滑石)
滑石は含水珪酸塩鉱物で、漢方でもよく用いています。その粉末5gを1 日分とし、3回に分けて飲みます。
③山バチの巣
山バチの巣やすずめバチ、その他ハチの巣は食べると尿路結石によいといわれております。
④レモン
果実をしばって大量に飲むと、結石をとかして排出する効果があります。
⑤梅干し
1~2個を熱い番茶でほぐし、湯のみ茶わんに1~2杯飲みます。
⑥パセリ
血管をしなやかに丈夫にする作用があって、結石の症状をやわらげます。毎日食べると効果があります。
⑦ハチミツ
湯でといて飲むと効きます。

| ね |
 |

|
寝汗
寝汗は睡眠中知らずに下着をぬらすほど大汗 をかくことで、盗汗ともいわれます。寝汗はかぜのひき始めや治りがけにもありますが、多くは呼吸器系が弱かったり、消耗性の疾患があったり、疲れやすい状態になっているときにかきます。
多くの場合、肩こりや頭痛、生理不順などを 伴います。一口にいえば、自律神経のバランスがくずれた結果です。
ただ夜間に目が覚めるような、いかにも病的な寝汗が毎晩つづくような場合は、結核、バセドウ病などの疑いがありますから注意してください。神経質な子どもの場合、日中に過労や精神興奮、欲求不満などがあると、しばしば大汗をかくことがあります。
■ツボ治療法
頭の百会、後ろ首の天柱、風池、背中の膈兪、腰の腎兪、志室を治療します。体の前面では、胸の膻中、腹部の中脘、関元、天枢、足では足三里、三陰交を処置します。知らず知らずのうちに五臓の疲れがとれ、寝汗をかかなくなります。
■民間薬
①黒マメ
疲れやすい人の寝汗に効果があります。黒マメの皮9gと小麦のフスマ9gを水で煎じて飲みます。子どもの虚弱体質で寝汗をすごくかくものは、黒豆を常食にするとよいです。
②ニラ
ニラを味噌あえにして、1日3回食ベます。味噌汁にしてもよいです。
③モモ
かぜや熱病の寝汗は、モモの実を食ベます。
④ヤマイモ
焼いて皮をむいて食べますが、煮ても、効果があります。
⑤モチ米・小麦
寝汗がひどい時は、モチ米と小麦を同量炒って粉末として、毎回10gを玄米スープで飲みます。また、豚肉とまぜて食べてもよいでしょう。
⑥シジミ
みそ汁の実にシジミをたくさん入れて食べます。

| の |
 |

|
脳卒中
脳卒中は脳の急激な循環障害により、突然倒れて意識を失い、運動マヒを示すものです。
脳卒中には、脳出血、脳血栓、脳塞栓、クモ膜下出血などがあります。そのほかに一過性脳虚血、 高血圧性脳症もあります。
脳卒中の予防には高血圧、脳動脈硬化などの早期治療・手当が大切です。日常生活の養生に注意し、発作が起きたら、医師にみてもらうまで動かさないことです。ひとたび脳卒中を起こしますと、元通りに治ることは困難なので、その予防に徹することがとくに重要です。
■ツボ治療法
第一にマッサージ施術を行います。背中の心兪、膈兪、三焦兪、おなかの大巨などを用いますが、手足の冷えるときは足の三陰交、体力をつける目的で腰の腎兪なども使用します。全身とくに足部のマッサージ、運動療法も行うとよいですが、いずれも症状が落ちついてから施術してください。
■民間薬
①ダイズ
脳卒中で倒れて口がきけなくなってしまった人には、ダイズが有効です。ダイズをたっぷりな水で、あめのようになるまでよく煮ます。これを少しずつ食べさせ続けると、口のもつれに大変効果があるといわれています。
②ダイコンめし
ダイコンは脳卒中の後遺症で、半身不随になった人によいといわれております。昔は脳溢血後の薬に、切り干大根の煎じ汁が用いられました。
③クワのひげ根
脳卒中で倒れて、軽い歩行困難に陥ったら、クワのひげ根を乾燥させ、煎じて飲ませますと、しびれがとれ、運動機能が回復するといわれます。
④ゴボウ
発作後の後遺症の回復に、ゴボウを煮て食べさせるとよいそうです。
<注意>①便秘に気をつける。便秘したら、アロ工の大きいのを1枚細かくきざんで食べる。②興奮性飲料または増強剤のようなものはさける。③食べすぎは禁物。④塩けと油けはなるべく減らすこと。⑤利尿をはかること。お茶がわりにトウモロコシの毛、ドクダミの煎じたものを飲む。⑥ぬるい湯で入浴をさかんにすること(全身浴があまりやれない人は局部浴でもよい)
| は |
 |

|
肺炎
肺炎は肺に炎症を起こす病気で、現在は抗生物質などの化学療法が発達しているため良く治るようになりましたが、それでも乳幼児、老人の死亡率からいえば、いまでも安心はできない病気です。
この病気はかぜ、気管支炎、百日ぜき、麻疹などに引き続いて起こりやすく、突然体温が40度以上に上がり、呼吸困難、軽いせきが出て胸が痛みます。子どもの肺炎では、顔面が赤くなるより、白くなる方が重症だといわれています。
また、重症なのに熱も高くなく、脈も多くならず、肺炎らしくみえない型もありますので、注意を要します。
肺炎にかかったら、まず安静第一です。そして、ビタミンの多い流動食をとることです。また専門医にも診てもらうようにしましょう。
■ツボ治療法
後ろ首の風池、背中の肺兪、厥陰兪、心兪、腰の腎兪、胸の中府、膻中、おなかの巨闕、期門、手の郄門、神門、孔最、俠白などが治療穴です。また病室の保温と湿度に気を配り、温度を一定に保つようにします。
■民間薬
①馬肉
馬の生肉で胸から背にかけて包み、湿布がわりにします。ふつう肺炎で発熱すると、胸部に痛みを覚えますが、馬肉はこの痛みや熱をとるのに有効とされています。用い方は、馬肉が腐敗してきたら、たびたび取りかえます。
②鯉の生血
鯉は黒い色をした真鯉のほうがよく、ヒ鯉では効果が薄いといわれています。とりたての鯉を塩でよく洗い頭を切って血をとり、できるだけ新鮮なうちに早く飲みます。生き血はさかずきに軽く1杯を1日分として、1回飲みます。
③ホウレン草
せきがひどい時は、ホウレン草の種を乾燥させ、とろ火で黄色くなるまで炒り、これを粉末にしたもの5gを1日2回飲みます。
④レンコン
すりおろしてしぼった汁をさかずきに1杯ずつ、1日3回飲みます。

| ひ |
 |

|
冷え症
冷え症とは手や足、腰に冷えを感じる症状で女性に圧倒的に多いものです。冷え症になると 頭痛、のぼせ、めまい、イライラなどを伴うことがあります。
冷え症は日本人にとくに多いといわれていますが、それだけで生命にかかわる病的状態でもないため、これについての本格的な研究は非常に少ないのです。
冷え症の原因についてはいろいろの説がありますが、その要因は自律神経の機能が不調になるためといわれ、その誘因として、内分泌障害や、皮下脂肪がたまることによる熱の放散があげられます。冷え症の人の多くが、神経質で、やせ型、貧血体質で、婦人では更年期に多いということからもその理由がわかります。
■ツボ治療法
冷えは、人間の血液分布の不均衡が下半身に生じやすいことから、足や腰に多いものです。そこで、ツボも足や腰を中心に選びます。
足では築賓と湧泉、腰では腎兪、大腸兪、上髎、次髎がポイントとなるツボです。そのほか、背中の厥陰兪、胸の膻中、おなかの肓兪、大巨を加えるとよいでしょう。
また、朝晩、布団の中で全身運動を分ずつ行い、日光浴も十分にやって下さい。
■民間葉
①サフラン
めしべを10本ほどお湯につけて飲みます。ブランデーを少量加えると効果的です。
②ダイコン
葉を干し、これで腰湯をします。
③ニンニク
ニンニクのハチミツ漬けを1日2~3片食べ続けると、冷え症が治るといわれます。
④ヨモギ
葉を綿代りにした座ぶとんに、いつも座るようにするのもよいでしょう。また、ヨモギの太い茎を刻んで乾燥させ、もめん袋に入れて風呂に入れると、よく効きます。
⑤クマ笹
エキスを適量にうすめ、常飲します。
⑥香辛料
ショウガ、ミョウガ、セリ、ネギ、ニラ、ノビル、サンショウ、コショウなども効果があります。
⑦ニンジン
おろしたり、煮て食べると、血液冷の循環をよくし、体が温まります。
皮膚瘙痒症
皮膚に発疹もなく、ただむやみにかゆくなるのが皮膚瘙痒症です。
かゆみの原因はいろいろで、ヒステリーなど心因性のものもあります。また老人で皮膚がカサカサしている場合も、かゆみが起こりがちです。
かゆみの原因を突き止め、それに対する治療をします。老人性の、皮膚の乾燥によるものは、入浴時のせっけん量を減らし、簡単な油性の骨薬を塗るだけでなおることも少なくありません。
皮膚をかいてしまうと、そのために炎症が起きますから、かかないように我慢することが大切です。
肌着などは、吸湿性のある木綿のものを用いましょう。
■ツボ治療法
主なツボとしては、背中の大椎、治喘、肺兪、膈兪、肝兪、脾兪、腰の腎兪、大腸兪、次髎、胸の中府、腹部の中脘、関元、腕の孔最、合谷、足の三陰交、足三里、太衝のツボを選びます。
■民間薬
①クマ笹風呂
クマ笹の葉や茎を用います。葉と茎を適当に切って、鍋で煎じます。その煎じ汁を風呂に入れるか、クマ笹を布袋に包み込み、これを風呂に浮かべるかします。入浴は最低5分間ぐらい2回以上入り、入浴後はシャワーなど使わず、そのまま上がります。皮膚のかゆみ がおさまります。
②ニンニク
適当に煎じたニンニク汁で洗うのも効果があります。陰部のかゆみにとくによいでしょう。
③オオバコ
オオバコの実や草を煎じた湯で洗っても効果があります。
④番茶
濃く煎じてさかずき2杯ほど温服します。のぼせからくる、むずがゆさに有効です。
⑤ユキノシタ
葉をしぼった青汁をさかずき1 杯ずつ飲みます。
 |

|
肥満
肥満が医学上問題になるのは、肥満のために伴う症状、たとえば動脈硬化、高血圧、糖尿病、心臓病、痛風、胆石、あるいは膝関節の疾患、腰痛などです。このような場合は、医師の診断のもとに治療を受ける必要があります。
ここでとり上げる肥満は、美容上問題になる肥満で、先に述べた症状を伴わず、太っている体そのものに問題を有する場合です。
一般的にみて、最も脂肪がつきやすいところは、まず、あごから両方の乳を結んだ線あたりまでと、へその下の腰回り、太もも、膝の後ろ側、足首などをあげることができます。
したがって、太りすぎないためには、まずこれらの場所に脂肪がたまらないような処置を講じることがポイントになります。
■ツボ治療法
胸の膻中、腹部の巨闕、中脘、天枢、陰交、 関元、大巨、脇腹の期門、背中の心兪、肝兪、 腰の三焦兪、腎兪、大腸兪、足の足三里、三陰交、手の合谷などが主要なツボになります。
また肥満には、全身マッサージによる全身療法が有効です。
■民間薬
①生野菜のジュース
1日約500ml(約3合)以上飲みながら減食すれば、健康に害なくやせられます。ジュースの材料は、ホウレンソウ、ニンジンの葉、キャベツ、カブの葉、トマト、セロリ、キュウリなどを適宜まぜ合わせます。
②ワカメ
ワカメなど、海草の酢のものを常食していれば、新陳代謝を高め、低カロリー食で、だんだんやせてきます。
③リンゴ酢
リンゴ酢を水で適当に薄めて、コップ1杯ぐらい食前に飲めば、効果があります。
④そばがき
ごはんがわりに、ときどきそばがきを食べます。
⑤コンニャクと寒天
どちらも満腹感が得られ、低カロリーですみます。食べる日を1週間に1 日決めておき、実行すればスマートな体になってきます。
疲勞倦怠感
疲労は筋肉などの体の使いすぎによって起こる生理現象で、病気ではありません。しかし疲労を重ねると、慢性疲労におちいります。そして、これからいろいろな病気に進むことも少なくありません。
その日の疲労はその日のうちに取り除くように、入浴、睡眠を心掛けること。日光浴、朝と夜、ふとんの中で運動をするようにしましょう。
慢性的な疲労感は、高血圧、ビタミン不足、糖尿病、腎臓病、結核、貧血、慢性胃腸病、肝炎などの病気の一つとして現われることがありますので、原因をさぐることが大切です。近視や遠視など、目が原因のことも少なくありません。何日も疲れやだるさが抜けない場合は、医 師の診断を受けてください。
■ツボ治療法
疲れやすいという体質を東洋医学では「腎虚症」と言います。こうした視点でツボを選びますと、腰の三焦兪、腎兪はエネルギーを体中にバランスよく取り入れる働きがあるため、重要です。また、背中の肝兪、胸の膻中、おなかの中脘、肓兪、関元、手の陽池、足の太谿、湧泉なども治療すると、疲れがとれます。
■民間薬
①ゴマ
黒ゴマは全身疲労の回復に効果があります。黒ゴマを炒ってすりつぶし、それにツルドクダミの根を細かくきざみ、すりつぶし、適 量のハチミツと水をまぜ、火にかけて水あめ状になったら、火からおろします。これを朝晩小さじ1杯ほどなめること。
②ニンニク
ニンニクをすりおろしたものを少量の小麦粉をまぜ合わせて疲労回復のツボ、土踏まずに貼るとよいです。
③ショウガ・ニンニク
ショウガとニンニクをつぶし、熱湯を注いで飲みます。全身の倦怠感 や脱力感、暑気あたりなどに効果があります。
④ケンチン汁
何をしても疲れてしまうという疲労が激しい時には豚肉や牛肉を入れたケンチン汁に、焼いたおモチを入れて食べると元気になります。出産後の体力増強によいでしょう。

| ふ |
 |

|
二日酔い
二日酔いは、多量のアルコールが体内に入って、それが抜けきれないために起こるもので一 種の中毒症状を起こしているということです。
そのために、胸のむかつき、嘔吐、頭痛、頭重、体のだるさ、食欲不振などを訴えます。
お酒もほどほどならよいのですが、どうしても飲みすぎてしまいがちで、そうなりますと胃や肝臓をやられてしまいますので、なかなか無理な注文かもしれませんが、お酒はホロ酔い程度にセーブすべきです。
二日酔いは時間がたてば徐々に治ってきますから、安静にして治るのを待つのがよいのです。迎え酒はよくありませんので、やめましょう。
早く気分をすっきりさせたいというとき、ツボ療法は役に立ちます。
■ツボ治療法
後ろ首の天柱、背中の心兪、肝兪、胃兪、腰の腎兪、胸の膻中、おなかの中脘、陰交、手の合谷、足の三里などが治療のポイントになります。この治療は、按摩、マッサージが最適で、気分がよくなってきます。
■民間薬
①クマ笹
エキスを適量に薄めて飲むとよいでしょう。交感神経の高ぶりを抑えてくれますし、また、少なくなった血糖の補給もしてくれますから、悪酔い、二日酔いを防ぎます。
②ダイコン
二日酔いの食欲不振に、ダイコンおろしのしぼり汁にハチミツを加えて飲みますとよいです。
③梅干し
梅干しをたくさん食べると元気が出ます。濃い番茶といっしょに食べるとよいでしょう。
④カキ
秋を代表するカキの実には、ビタミンCがたっぷり含まれており、またブドウ糖、果糖の含有量が多いので、二日酔いにたいへんよく効きます。
⑤レモン
レモンも二日酔いに有効です。ハチミツを加えると、さらによいでしょう。
不妊症
不妊症とは結婚した夫婦が性生活を3年以上続けても、子供ができない場合をいいます。現在では、その原因の半分が男性側にあることがわかっています。
男性側に不妊症の原因がある場合は、大部分が精液の異常で、精子の形成障害、無精子、精子の通路になっている部分の障害、性交障害などがその原因の主なものです。
女性側の原因は、①排卵障害、②卵管の異常、③子宮の発育異常、などです。
そのほか、精神的なストレスも影響します。ともかく、専門医によくしらべてもらいましょう。時により、私たち鍼灸師も子さずけの神にならせていただいています。ツボ刺激は、女性の体の機能を円滑にしてくれます。
■ツボ治療法
背中の膈兪、肝兪、脾兪、腰や臀部の腎兪、次髎、中髎、膀胱兪、胞肓、腹部の中脘、肓兪、気海、中極、足の血海、曲泉、陰陵泉、三陰交、復溜、太谿、太衝などから選んで治療をします。
また、肩や腰にホットパックをし、骨盤内の血液の循環をよくするために、赤外線の照射をするとよいでしょう。
■民間薬
①クマ笹風呂
昔から子宝の湯、または婦人の秘湯として親しまれています。作り方は、クマ笹を取って来て、大きな鍋かお釜でゆで、その汁を風呂の中に入れ、また木綿の袋に入れて浮かせて入浴するとよいのです。
②トウキ
昔から婦人薬として使われています。 乾燥したトウキ3gを1日量として、飲むとよいです。
③ハトムギ
ハトムギのおかゆを常食にします。
④ゴボウ酒
不妊は生理不順が伴う場合もあります。細かくきざんだゴボウをひとつかみガーゼにくるんで、約1ℓの日本酒に漬け込み、1 週間ほどしたら空腹時にさかずき1杯飲みます。
⑤サフラン
5本を湯のみ茶碗に入れ、冷ましてから上ずみ液を飲みます。5時間たったら、また飲み、色の出なくなるまで飲むとよいです。
 |

|
不眠症
健康の最大のポイントは、睡眠をよくとることですが、世の中には寝るほどの薬を知らないどころか、痛切に眠りを求めながら、それができない不眠症の人が非常に多いものです。
不眠症のタイプにはいろいろありますが、寝つきの悪いもの、何度も目が覚めるもの、朝むやみに早くから目が覚めるもの等々ですが、原因の大部分は精神的なものです。体の異常があって眠れないことも少なくありません。
眠れない時は意識しすぎないで、リラックスすることです。高年者の場合、自律神経失調症 となり、身体のバランスがくずれて不眠症となる場合もあります。
この場合も、ツボ治療法はたいへんよく効きます。
■ツボ治療法
後ろ首の天柱、背骨の膈兪、肝兪、おなかの鳩尾、期門、足底の湧泉などが治療穴です。灸治療には膈兪、肝兪、巨闕、期門を1カ所、3 ~5壮、1日1回毎日続けます。眠れないからといって、睡眠薬や精神安定剤の乱用は慎みましょう。不眠で死ぬようなことはありません。
■民間薬
①タマネギ
世界中で広く行われている解消法は、生の玉ネギまたは長ねぎをきざんで枕元に置くだけの方法です。タマネギの揮発成分が神経を安定させてくれるようです。
②クマ笹
神経がイライラして眠れない時は、クマ笹エキスを適量お湯に薄めて飲むと、グッスリ眠れます。
③ミッバ
ミッバをおひたしやあえ物などにして、たくさん食べましょう。
④シソ酒
シソの神経を鎮める効果と適量アルコールとの作用で、よく眠れます。シソを半日くらい水切りしてからふきとって、びんに入れ、焼酎と氷砂糖を入れます。3カ月ほどしたら、シソを取り出します。そして、シソ酒を寝る前に飲みます。
⑤ニラ
体が温まり、よく眠れます。

| へ |
 |

|
变形性膝閃節症
中高年になると、膝の痛みを訴える人が多くなります。そのため長道が歩けない、正座ができない、といったことにもなります。中高年に多く起こる膝関節の故障を、変形性膝関節症といいます。
これもいわば一種の老化現象で、膝関節をつくっている大腿骨と脛骨のかみ合わせ面のクッションの役目をしている軟骨の一部がはがれ、骨と骨が触れ合ったり、関節のへりに骨棘が形成されるようになって、そのため痛みが生じるようになるのです。
それに加えて、関節の周りを包んでいる関節包の内面の滑膜や、関節をとり巻くように補強している靱帯などの弾力性や柔軟性が失われてくるため、膝の動きが悪くなるわけです。
■ツボ治療法
足の委中、承山、足三里、梁丘、湧泉、腰の腎兪、志室、居髎、大腸兪などがポイントになります。また、灸治療では膝のすぐ下の犢鼻と膝裏の委中が重要なツボです。
変形性膝関節症には、鍼治療がよく効きます。膝関節の痛みは、老化現象とともに、多くの場合は太りすぎも関係していますから、減量することも大切です。
■民間薬
①ドジョウ
ドジョウ2匹をさいて骨を抜き、皮の方を患部に貼って湿布します。はれて痛む時は、とくに有効です。
②オダマキ
茎と葉をつぶし、その液汁を痛む関節に塗ります。
③サトイモ
サトイモ2~3個の皮をむいたものに、ショウガの小さいもの1個をすりおろし、これに同量の小麦粉を加えて、よく練ってまぜ合わせます。これを布かガーゼにのばして、寝る前に貼ります。痛みがやわらぎます。
④サンショウ
サンショウの実を煎じて飲みます。食前30分にコップ1杯ずつ飲みます。胃も丈夫になって、発汗、解熱作用もあります。
⑤ネギ
ネギの青いところも白いところもいっしょに煮て、その汁を飲みます。
扁桃炎
扁桃炎はかぜ、はしか、ジフテリアなどの感染症や疲労、気候の変化などで起こる病気です。
症状は39~40度くらいの高熱や、のどの強い痛みが特徴で、とくに物を飲みこむときに強くなります。関節痛をみることもあります。
慢性化すると熱や痛みがないのに、肩がこり、ときには腎炎、リウマチ熱、心内膜炎などを併発することもありますので、注意を要します。
■ツボ治療法
急性扁桃炎の場合は、鍼治療がよく効きます。ツボは首の廉泉、のど元の天突、背中の大椎、手の合谷、孔最が用いられます。もちろん、マッサージ、指圧、灸も効果があります。ただし、38度以上の熱があるときなどは避けます。
扁桃炎が慢性化すると 、のどのはれや声がれなどとともに、かぜをひきやすくなったりします。慢性のときは、前記の廉泉、天突、大椎、合谷などのほか、背中の肺兪、足の三里のツボがポイントになります。
■民間薬
①ショウガ湯
ショウガのおろしたものとカラシ各さかづき1杯に、水を1升加えて火にかけて、熱くなったらタオルを四つ折にして両端を持ちながらこれを浸してのどに当て、その上から乾いたタオルで軽くしばって押えます。冷えたらもう一度湯に浸して、20分間ほど2~3回繰り返します。
②メンソレターム
メンソレタームやタイガーバームなどを耳の下からのどぼとけにかけてぬり、そのあとを手のひらで軽擦します。
③ハチの巣
足長蜂(蜂の子が入っていないもの)を煎じて飲みます。他の蜂の巣でも効果があるようです。
④ユキノシタ
ユキノシタの生薬を塩でもんで、桃出た汁を脱脂綿などにつけて、のどにぬると、のどの痛みがとれます。
 |

|
便秘
一般的には3日以上排便がなく、便が長時間大腸の中にとどまっているのが便秘です。しかし、個人差があって、1日1回排便があっても、量が非常に少なかったり、便がかたくて出にくいのも便秘といえます。
便秘の中で最も多いのは常習性便秘で、ことに女性に多く、日本女性の7割は便秘症といわれるほどです。常習性便秘の多くは、腸のぜん動運動が低下して起こるとされており、運動不足が加わると、さらに便秘症状が進みます。
便秘が長く続くと、肥満、ニキビ、シミの原因になるだけでなく、疲れやすくなり、いつまでも倦怠感が残ります。また女性の生理や胃腸、肝臓、心臓その他の病気を誘発する引きがねにもなります。
■ツボ治療法
背中の肝散、脾兪、三焦兪、腰の大腸兪、小腸兪、おなかの中脘、天枢、大巨、腕の曲池、 支溝、三里、足の三里などのツボが使用されます。鍼灸のほかにも、按摩、マッサージ、指圧なども効果があります。
■民間薬
①クマ笹
エキスを適量に薄めて、毎朝空腹時に飲むと、効果があります。
②アロエ
慢性便秘によく効きます。アロエをそのままかじるか、あるいはすりおろして食べてもよいですし、煎じてもよいです。
③ジャガイモ
新鮮なジャガイモの芽をとり、よく洗ってすりおろし、布にくるんでしぼった汁を1回に大さじ2杯、1日2回空腹時に飲みます。
④クルミ・黒ゴマ
クルミ60gをつきまぜて、 毎朝1さじ飲みます。
⑤ドクタミ
花を咲かせたドクダミを採取して、 天日で干し、2~3gほどをヤカンで煮つめて煎じ、お茶がわりに飲みます。
⑥サツマイモ
サツマイモはジャガイモの約2 倍の繊維があり、排便を促進してくれます。
| ま |
 |

|
慢性関節リウマチ
慢性関節リウマチは、膠原病といわれる病気の一つで、関節だけではなくて全身の病気です。
人間の体には、内臓の壁をつくったり、組織すき間をすずめたりする結合組織があります。この組織をつくっている線維の主体を膠原線維といいますが、この全身の結合組織が腫れて熱をもって痛んでくるのが、膠原病です。
関節リウマチの原因は、自己免疫説などが言われていますが、いずれにしろ、朝起きたとき指が動きにくい、こわばるといった症状が関節リウマチの初期症状で、左右の関節が対称的におかされていって痛みが繰り返して起こったり、続いて痛んだりします。そして、病気はしだいに大きな関節に進んで、指から手、ひじ、足、膝というように痛んでいきます。
■ツボ治療法
それぞれ痛むところを治療しますが、基本的なものとして、背部の肝兪、脾兪、腰部の腎兪、腹部の中脘、天枢、大巨、ひじの曲池、手首の陽池、膝の内膝眼、外膝眼、足首の解谿などがあげられます。また便通をよくし、軽い全身運動をしてください。
■民間薬
①ショウガおろし
痛みをやわらげるのに、おろしショウガを用います。ショウガの温湿布を患部に当てると、楽になります。またショウガをすりおろし、しぼった汁をお湯にたらし、タオルをつけてしぼり、患部に当てます。3~5 回、タオルをしぼり直し、肌に赤みがさすくらいに温めると、痛みがやわらぎます。
②松葉エキス
松葉エキスを飲むと、リウマチに効果があるといわれています。エキスを毎食前さかずき1~2杯飲むようにします。
③シソの葉風呂
もめん袋にシソの葉と茎を入れ、湯舟に入れます。身体がよく温まり、痛みがやわらぎます。
④ハトムギ
ハトムギおかゆを常食とします。
⑤キュウリとニンジン
それぞれすりおろして、 まぜて飲みます。
慢性気管支炎
慢性気管支炎は、せきと痰が主症状です。一般に起床時に出ることが多く、痰の色もいろいろですが、色がつくのはよい状態ではありません。
特に悪化しやすいのは、秋から冬にかけてですので、秋になってせきを伴うかぜ症状が始まったら注意して、早期に治療することが必要です。
慢性気管支炎は、大気汚染、タバコの吸いすぎ、刺激性のガス、粉塵などと密接な関係があり、なかなか治りにくい病気です。また、体質的にかかりやすい人もおり、慢性気管支炎にかかったら、医師と相談をして長期的な治療計画をたててもらうことが大切です。
この病気は長期にわたりますので、気管支内に痰がたまらないようにして、細菌の増殖を防ぐことが重要です。
■ツボ治療法
のど元の天突、水突、胸の中府、後ろ首の風池、背中の肺兪、腰の腎兪、腕の俠白、孔最などの諸穴を使用します。足の三里も治療しましょう。また呼吸筋をきたえるために、1日2~3 回、1日に10分ほど腹式呼吸をすると、効果があります。
■民間薬
①クロマメ
クロマメ大さじ2杯を360mlの水でせんじ、そのせんじ汁を飲みます。
②ニンジンおろし
ニンジンをすりおろし、そのまま食べるか、すりおろしたものを布でしばって汁をとり、1回にさかずき2杯ほど飲みます。ニンジンは気管支粘膜を強め、抵抗力を増加させる働きがあります。
③クマ笹
エキスを湯飲み茶わん1杯ぐらいの湯で薄めて飲みます。
④レンコン
節をすりおろし、湯の中に入れて飲みます。セキがとまります。
⑤大根あめ
ダイコンを輪切りにし、水あめの中に入れておくと、あめの汁ができます。それに熱湯を加えて飲みます。あるいは大根おろしを作って、その中にあめを入れて飲んでもよいのです。
 |

|
慢性鼻炎・蓄膿症
慢性鼻炎は急性鼻炎から移行したものや、副鼻腔炎、腺様増殖症、職業性などから起こることもあります。肥厚性のものと萎縮性のものとがあります。
蓄膿症は副鼻腔に急性の炎症が起こり、膿汁がたまったり、これが慢性化したりしたもので、頭痛、鼻づまり、頭重感、嗅覚障害などを訴えるようになります。また注意力が低下したりします。鼻腔内には膿汁や鼻茸などが認められます。
鼻炎は3~4日で治ることもありますが、蓄膿症はなかなか治りにくいものです。体質的なことも考えられますので、体質改善を計ることもよいと思いますが、専門医の指示を受け、根治させることです。
■ツボ治療法
頭と顔にある百会と睛明、迎香の3つが特効ツボです。さらに、のど元の天突、背中の大椎、足のくるぶしの盛り上がりの少し下にある飛陽も大切なツボです。鍼や灸でもよいですし、指先を使った指圧か、指ハリ刺激もよく効きます。押し方は少し痛いくらいにぐっと強く押すのがコツです。一押し3~5秒くらい、3~5回押します。
■民間薬
①クマ笹
クマ笹エキスを適量に薄めて一日に 3~4回飲みます。またエキスを患部に点滴するのもよいでしょう。
②ドクダミ
生の葉を4~5枚塩でもみ、汁が出てくちゃくちゃになるくらいまでにしたものをまるめて、鼻の中に30分ぐらい詰めておきます。取り出したあと、鼻を静かにかみます。鼻づまりには、とくによいようです。
③フキ
茎を2cmぐらいに切り、就寝前に鼻孔に入れておきます。片方ずつ行います。
④アロエ
しぼり汁を2~3滴、鼻孔に入れます。
⑤ネギ
ネギの白根を細かくきざんで茶わんに入れ、熱湯を注いでいっぱいに満たします。これに少量のみそを加えてまぜ、1日2~3回飲みます。

| む |
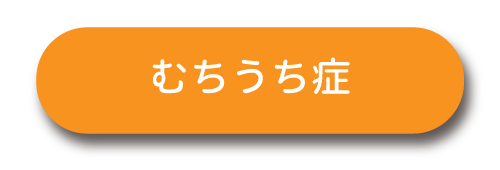 |

|
むちうち症
正式には、頸椎ねんざといいます。自動車の追突などの事故で、急に強い衝撃を受けると、首の骨に一時的にねんざの症状が起きます。肩がこる、頭が痛む、耳鳴りがする、腕がしびれるといった自覚症状があります。
したがって、一時思われていた不治の病ではありません。
事故にあったら、必ず早いうちに医師にみてもらうことが必要です。治療は、ふつう初期のころには、固定して安静が必要です。
しかし3カ月以上固定しておくのはかえってよくありませんので、6週間前後で軽いマッサージや垂直牽引が行われることもあります。むち打ち症の初期には、損傷部にはれや熱があるので、湿布薬を用います。
■ツボ治療法
後ろ首の天柱、風池、完骨、肩の肩井、肩髃、首の根元の大椎、手の曲池、尺沢、少海、内関、神門、合谷などが主として使用されます。
症状が慢性化している患者に対しては、お灸療法がたいへん効果があります。また、図の矢印の方向にゆっくりとマッサージとともに、指圧をすると、さらに効果的です。
■民間薬
①ツワブキ
ツワブキの葉を2~3枚患部に当てて、その上から包帯をします。熱で葉がしおれたら取りかえます。ひんやりと冷たく、気持ちよく熱を取ってくれます。
②キハダ
粉末を酢で練り、それに卵の白みをまぜ、布か日本紙にのばして貼ります。
③ハコベ
ハコベを鉢で繊維が残らないようにすりつぶし、これに酢と小麦粉を加えて、患部に貼って、繰り返し取りかえます。
④オトギリソウ
5~15gを約500mlの水で半量に煎じて、1日3回に分けて飲みます。
⑤イヌザンショウ
日干しにした葉をできるだけ粉末にし、卵白を加えてねり合わせます。これに少量の小麦粉を加えてまぜ、患部に厚く塗ります。上から布を当て、軽く押さえておきます。

| め |
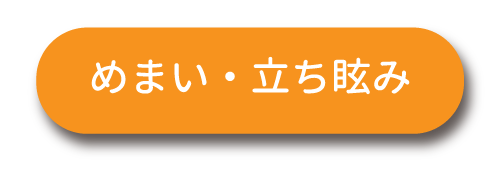 |

|
めまい・立ちくらみ
突然、自分の周囲がグルグル回っているような感じにおそわれるのが、めまいの症状です。
また、急に立ち上がったとき、つまり頭の位置を変えたとき、瞬間的に頭がフラフラッとする症状を立ちくらみといいます。
どちらも平衡感覚の異常です。めまい、立ちくらみは、耳のいちばん奥の内耳から起こります。ここに体の平衡を保つ三半規官という規官があり、ここでの機能異常がめまいや立ちくらみになるのです。
ですから、耳から大脳、小脳といった機能に、あるときに障害があらわれて、脳貧血、脳充血、更年期障害、船酔い、胃腸の病気、神経症などから目まい、立ちくらみが起こるわけです。とくに更年期の症状として、よくみられます。
■ツボ治療法
めまいや立ちくらみも、内耳の平衡感覚をつかさどる部分の異常ですから、耳の周囲によく効くツボがあります。耳の後ろにある竅陰と耳たぶの下にある翳風です。そのほか、後ろ首の天柱、背中の心兪、肝兪、腹部の中脘、 肓兪、足の丘墟もあわせて治療すると、いっそう効果的です。
■民間薬
①クルミ
実を食べると、めまいや耳鳴りに効くといわれます。
②野菜の青汁
カブの葉、ホウレンソウ、ダイコンの葉、キャベツ、ニンジンの葉などをジューサーでしぼり、青汁をつくって飲みます。
③クチナシの実の黒焼き
クチナシの実を黒焼きにしたもの2gを酒で飲みますが、お湯でもかまいません。
④ケイガイ
別名シソ科アリタソウといいますが、穂の粉末を1日に8g飲みます。産後のめまいによく効くといわれます。
⑤キク
花を日干しにし、1日量5~8gを約500mlの水で半量に煎じて、食間に飲みます。
⑥サフラン
サフランのめしべを数本、熱湯の中に入れて振り出し、温服すると、めまい、立ちくらみによいといわれます。
| や |
 |

|
夜尿症
人間の排尿機構が完成するのは、3~4歳と考えられています。この時期を過ぎても、夜間に排尿の失敗をするものを夜尿症といいます。
夜尿症には、なんらかの病気がひそんでいる場合もあります。尿崩症、萎縮腎、萎縮膀胱、膀胱炎、尿道炎、外陰炎、膣炎などです。さらに、膀胱を支配している神経に異常がある場合もあります。
しかし、こうした病的なものは夜尿症のほんの一部で、ほとんどは膀胱などになんの異常もないのに、自分が意識することなしに、夜間に正常と同じ排尿行為をしてしまうのです。
原因でよく指摘されるのは、精神的、心理的な要因です。日ごろの習慣、不規則な生活も原因となります。
また体の冷えが原因である、ということもいわれています。
■ツボ治療法
背中の身柱、腰の腎兪、志室、膀胱兪、次髎、腹部の水分、関元、中極、足の三陰交、太谿、大敦などが主なツボです。
夜尿症には、昔から灸治療がよく効くといわれています。治療とともに、母親はあまりクヨクヨせず、神経質に怒らないようにしましょう。
■民間薬
①塩
寝る前に塩をなめさせること。体の中に水分をたくわえるためです。
②餅
寝る前に焼きたての餅を1、2 個食べるとよいです。餅は利尿抑制作用があります。
③ビワ
葉の毛を取って洗い、干したものを1回4g煮つめて、食前1時間前に飲みます。
④ギンナン
寝る前に焼きたてのギンナンを5 個食べます。
⑤ニンジン
根の皮を少し焦げるくらいに焼いて熱いうちに食べます。中くらいのニンジン1本あれば、2回に使用できます。
⑥ニラ
毎日の食事に加えて食べさせます。
⑦シソ
葉を煎じて飲ませます。
また寝る前にあまり水分をとらせないこと。 夜よく体を温めることが必要です。

| よ |
 |

|
腰痛
腰が痛いというのはたいへん一般的な症状で、80%の人が一生のうちに一度は腰痛を起こすといわれています。
人は立って歩きますので、上半身の重みが腰にかかります。また、おなかには胃腸などの消化器や、いろいろな内臓を抱えていますので、腰は故障の起きやすいところです。
腰痛の原因は大きく分けますと、腰の筋肉の疲れからくるもの、これを腰筋痛といいます。また中高年層になって、腰の骨の変形がもとで起こる、いわゆる変形性腰椎症。無理な姿勢をしたときに急に起こるギックリ腰の腰痛。そして、いろいろな内科の病気から起こる関連痛の腰痛です。これらの痛みをやわらげるのが、ツボ治療法です。
■ツボ治療法
腰の腎兪、大腸兪、志室、それから腎兪から指1本半だけ上にいったところにある三焦兪が腰のたいせつなツボです。
腰が痛いと、姿勢が前かがみになって、おなかの筋肉が緊張しますので、へその両側の天枢も大切です。さらに足の承山と解谿の2つのツボも活用します。
■民間薬
①梅干し
毎日2個ずつ食べます。梅干しに含まれているクエン酸が、有害な老廃物を体外に排出して、腰痛を体の中から治していきます。
②そば粉
熱湯でねって、そばがきを作ります。これを毎朝、湯飲み茶わん1杯食べていると、冷えからくる腰痛に効果があるます。
③レモン
しぼり汁を茶さじ1~2杯ずつ、1 日3回飲みます。水や湯で薄めてもよいです。
④マツバ
一つかみほどを煎じて飲みます。
⑤ドクダミ
陰干しにした全草10~20gほどを 1日量とし、煎じて飲みます。また、ドクダミの葉を入れた薬湯に入浴します。
⑥ハトムギ
実の外皮をとり除いたもの10~20gほどを1日量とし、煎じて飲みます。
⑦ダイコンの薬浴
ダイコンの干葉でたてた薬湯に入浴します。